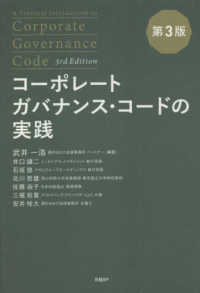出版社内容情報
幼児期の子の「困りごと」に向き合い、自己肯定感を高める接し方のコツとアイデアが満載!
本書は、親にとっては難しい「しつけ」について、「非認知能力」という観点から対処法を考えていく本です。子育てをしていると、つい、目に見える「できる」ことに囚われて焦りを感じてしまいがちです。けれども、本当は、目に見えにくい子どもの「心」や「社会性」に着目することが大事です。それは、これまで考えられていた「しつけ」というイメージとは少し違っているかもしれません。
非認知能力などと言うと、何か特別なトレーニングやしつけをして育てる力のように思われがちですが、そうではありません。非認知能力は、何気なくしている日々の子育ての中で育つものです。子どもに愛情をもって育て、毎日、ごはんを食べさせたり、歯磨きや着替えをさせたり、楽しく遊ぶことを大事にしたりするなど、日々のあたりまえの生活の中で自然と育つものだとも言えます。
つまり、日々の子育ての中ですでにやっていることの中に大切なことがあるのです。子どもに向き合おうという姿勢の中に、すでに非認知能力を育むために重要なしつけ的なものがあるのだと思います。
子育ては「魔法の言葉かけ」をすれば大丈夫というわけにはいきません。親ができることは、その子の「いま」をちょっとでも幸せが実感できるようものにするように、かかわることです。子どもと親の両者のハピネスが、子どもの自己肯定感を自然と高めることになり、よい影響を与えます。これが「しつけない子育て」です。
本書では、「食べない」「歯磨きをいやがる」「騒ぐ」「嘘をつく」などといった生活に関わる困りごとや学習面の困りごとについて、「しつけない」で対応する方法を、具体例豊富に紹介します。
内容説明
子どもの自己肯定感を高める接し方のコツとアイデアが満載!
目次
第1部 非認知能力を育てる「しつけない」しつけとは?(子どもにイライラしていませんか?―子育てが難しい時代;しつけストレス;「しつけ」って何?;どなったり、たたいたりはダメなの?―体罰によるしつけの悪影響;「強制型しつけ」と「共有型しつけ」 ほか)
第2部 非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシピ(「しつけない」しつけ1「生活の基本」編;「しつけない」しつけ2「人とのかかわり」編;「しつけない」しつけ3「育ちと学び」編)
著者等紹介
大豆生田啓友[オオマメウダヒロトモ]
玉川大学教育学部教授。1965年、栃木県生まれ。専門は、乳幼児教育学・子育て支援。青山学院大学大学院教育学専攻修了後、青山学院幼稚園教諭などを経て現職。日本保育学会理事、こども環境学会理事。NHK Eテレ「すくすく子育て」をはじめ、テレビ出演や講演活動など幅広く活動中
大豆生田千夏[オオマメウダチカ]
臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士。長年子育て相談にかかわる。親を指導するのではなく、親自身の力を認めファシリテーションすることを第一とし、カナダで生まれた未就学児の親のための「ノーバディズ・パーフェクト(NP)プログラム」(子ども家庭リソースセンター)や「赤ちゃんと創るわたしの家族(FS)プログラム」(子どもと家族支援研究センター)を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりん
jenny
hahihuheholy
さんた
septiembre
-

- DVD
- 投稿 怨霊映像64 吠篇