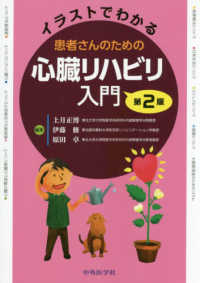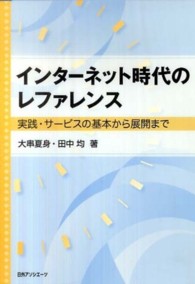出版社内容情報
経済学は、なぜ人間の生から乖離し、人間の幸福にはまったく役立たなくなってしまったのか? 経済学の堕落の跡をたどると同時にその再生の可能を探る。「科学的客観性」「ヴァリューフリー」を標榜し、いつしか「人間の心」を失ってしまった経済学。19世紀後半ドイツにおいて始まった経済学「科学化」の動き。ハイエク、「ゲーム理論」、さらには「シカゴ学派」の「ゴッドファーザー」シュルツへと至る、極端な経済の自由化と「脱倫理化」の強化。そして「クズネッツ曲線」をめぐる「新自由主義」の欺瞞。その一方での、上記の流れに抗して「人間の顔をした経済学」を目指した、ポランニー、イリイチ、あるいはウォーラーステインら世界システム論者などにによる、経済学における「社会的公正」理念復権への模索。経済学の歩みを「自由」と「正義」という二つの相対立する思想の相克の歴史と捉え、21世紀の「来たるべき経済学」の可能性を探る。
内容説明
なぜ人間の幸福に役に立たなくなったのか?緩んだ学問に終止符を!
目次
第1部 経済学の分岐点―倫理から倫理「フリー」へ(市場は「自由競争」に任せるべきか―理念と方法を問う;「暮らし」か「進歩」か―ダーウィニズムと経済学;「逸脱」のはじまり;経済学からの「価値」の切り離し―「社会主義経済計算論争」の行方)
第2部 「アメリカニズム」という倒錯(「自由」か「生存」か―大戦間期の「平和」の現実;マネジメント=市場の「見える手」;経済成長への強迫観念と、新たな倒錯のはじまり;“特別編”工業化される「農」―食にみるアメリカニズム)
第3部 新たな経済学の可能性をもとめて―擬制商品(フィクション的商品)の呪縛から離れて(世界システム分析の登場;「人間」をとりもどす―「労働」から「人間」へ;「おカネ」とはなにか―「レント」および「負債」をめぐる思考;「土地」とはなにか―そして「誰かと共に食べて生きること」)
著者等紹介
中山智香子[ナカヤマチカコ]
1964年生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科理論経済学・経済史専攻博士後期課程単位取得退学、ウィーン大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。専門は社会思想史、経済思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 虎と花~虎王の花嫁さんスピンオフ~【マ…
-

- 電子書籍
- 時時雨GRAFFITI【タテ読み】(1…