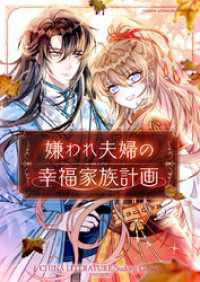出版社内容情報
ミュージアムに入れば物の見方がガラリと変わり、3年後、10年後の生活の糧となる。脳科学と博物館学の権威による脳に効く対談。
目次
はじめに ミュージアムは脳に似ている
第1章 ミュージアムの誕生―その華麗にして妖しい魅力に満ちた世界
第2章 ミュージアム、その陰の部分―論争・ワケあり・ヤバいもの
第3章 実際に鑑賞してみる―どんな作品をどのように観たらよいか?
第4章 これからのミュージアム体験―アートはなぜ必要なのか?
おわりに 日本は世界に類を見ないミュージアム大国
著者等紹介
中野信子[ナカノノブコ]
1975年、東京都生まれ。脳科学者、医学博士。認知科学者。東京大学工学部卒業。同大学院医学系研究科博士課程修了。フランス国立研究所ニューロスピンに勤務後、帰国。現在、東日本国際大学教授
熊澤弘[クマザワヒロシ]
1970年生まれ。東京藝術大学大学美術館准教授。西洋美術史、博物館学が専門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
94
脳科学者・中野信子が東京藝大大学院国際藝術創造研究科でキュレーションについて学んでいるのも驚きだが、対談相手の東京藝大熊澤准教授も生徒に中野氏がいてさぞ驚いたことだろう。ミュージアムは、脳と同じ構造で社会における記憶倉庫であり、展覧会は意識にあがっているものだと言う視点は新鮮だったが、中野氏が生徒としての立場を超えてパラダイムを転換する程の会話にはなっておらず、熊澤氏の専門の博物館学の講義が多くてやや期待はずれだった。大学院卒業後は、是非美意識と脳の関連をアートで結びつけるキュレーターになって頂きたい。2020/10/24
tamami
58
東京芸大大学院でキュレーションについて講義する熊澤さんと聴講者の中野さん二人の対談本。博物館・美術館の歴史、様々な作品や物産が館で展示されるまでの舞台裏、特色ある博物館・美術館の紹介など、盛りだくさんな内容。また、制作者についての情報や作品が館に収蔵されるまでの来歴等々、個々の作品を鑑賞するときに有益な事柄を具体的事例を元に語っている。熊澤さんによれば、日本全国には合わせて五千を超える博物館(博物館、美術館、動物園、動植物園)があるという。身近な博物館・美術館見学の際の必携として本書を薦めたい。2021/03/31
gtn
32
脳は身体全体のわずかしかないが、その機能を維持するために多大なエネルギーが必要と述べる中野氏。国家百年の計の視点から文化財や図書の保護に傾注すべきと主張する熊澤氏。共通するのは、見えにくいものにこそコストをかけろということ。政治や行政もそう。経常予算を確保し、真に必要な事業を着実に執行することが大事。政治家が花火を打ち上げ、臨時予算を付けて行うパフォーマンスが実を結ぶことはほとんどない。2021/08/22
りー
28
脳科学者と芸大美術館准教授の対談。美術館・博物館の来し方と未来への展望を語っている。それにしても、まぁなんというか、日本の文化行政の貧しさと展望の無さよトホホ…という慨嘆が行間から聞こえてくるようだった。韓国みたいに国ぐるみで振り切って、海外向け外貨獲得コンテンツとして文化を位置付けるのも良し悪しだけれど。予算が無い、人が足りない、国として文化をどう捉えてこの国の未来へ遺していくか、というグランド・ビジョンが全く無い!!そんな中で個々の館の頑張りが光っている。 2023/07/29
Sakie
24
ミュージアムとは『コレクションを収集・保管・調査研究し、展示公開に供する施設』。ミュージアムに関するあれこれについての対談である。中野さんがこのテーマに関心を持ったきっかけは、脳とミュージアムの機能が似ているからとある。整理すると、情報や知識の蓄積装置としての機能、表に出ない部分が肝心な機能を担っている点、インプットが即役立つとは限らず、何年も後になって活きることがある点だろう。興味のある分野が増えることはその人にとって幸せなこと、新たな可能性を拓くことである。学べる刺激が多くある点だけは都会が羨ましい。2021/02/21