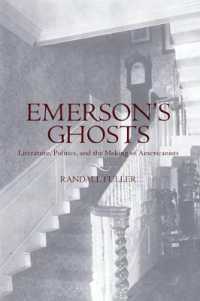内容説明
笑いは良いものなのか、それとも悪いものなのか。日常のさまざまな状況や関係の中に生まれる笑いについて、西洋哲学は「優越感」を、あるいは「小心さ」を見た。しかし、そもそも笑いという現象を解く一個の原理があるのだろうか。本書では「笑いとは平穏な日常の破裂である」という視点から、「優越」「不一致」「ユーモア」の笑いを分析、日本社会の笑いの状況を見渡しつつ、秩序・掟への揺さぶりとしての笑いの可能性を考える。
目次
第1章 優越の笑い(優越の笑いと笑ってはいけない問題;笑ってはいけない問題とステレオタイプ;優越の笑いが変容するとき)
第2章 不一致の笑い(不一致の笑いについて;「笑いの空間」の成立条件;「笑わせる者」と「笑う者」とのすれ違い)
第3章 ユーモアの笑い(ユーモアと気分の感染;日本社会とユーモア;お笑い以外のユーモア戦略;日本社会の中でユーモアが育まれる条件)
著者等紹介
木村覚[キムラサトル]
1971年生まれ。上智大学文学部哲学科卒業。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は美学、ダンス研究。現在、日本女子大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mc6ρ助
11
『要するに、優越感をベースにした自虐の笑いに勤しんでばかりの日本人は「未成熟」ではないかというのが、TAMAYO が日本の笑いを批判する主要ポイントである。・・「成長」なき笑いに陥っているという指摘は、厳しいが現在の日本にも当て嵌まるように思われる。(p217)』著者が執拗に「笑いの哲学」を追究したにもかかわらず、結局ここに落ち着いてしまうところがやるせない。2020/12/02
かんがく
10
筆者が例に出す芸人は綾小路きみまろ、毒蝮三太夫、ダウンタウン、オードリー、ナイツ、コロッケ、ザコシ、バカリズム、スギちゃん、濱田祐太郎など幅広く、それに対してベルクソン、カント、キルケゴール、ジジェクなど様々な哲学者の論考を用いて分析を進めていく。優越の笑い(いじりと自虐)、不一致の笑い(あるあるとズラし)、ユーモアの笑い(価値破壊的な笑い?これが一番難しい)の三章から社会と笑いの関係について述べており、ありがちな「日本の笑いは遅れてる」論で終わることなく、筆者のお笑い愛が伝わってきた。2024/02/04
かやは
10
笑いにするためには、常識を知らなければならない。芸人がコメンテーターとして重宝されるのは事柄に対しての視線が一般のものとは異なるからだろう。ナイツがかなり取り上げられていて、彼らのネタは知識があっても無くても笑える二重構造の笑いになっているという。2021年のM-1で、真空ジェシカがセンスがあると褒められたけれど点数が伸び悩んだことを思い出した。死にゆく運命を知っているからこそ、我々人間にはユーモアが必要。自分の愚かさを笑えるようになれば生きるのが楽になるのだろう。2022/04/18
hakootoko
7
“The Rise of victimhood culture”という未翻訳のポリコレ批判本の紹介があったので、綿野『さべいけ』再読へ。2021/11/19
tieckP(ティークP)
7
こういうことやりたいな、と思うことをやっていて、そこにいろいろな哲学者と日本の芸人が詰め込まれていて、またお笑いが好きなのも伝わってくるので好きな本である。その好きが九割という気持ちの上で言えば、僕とはペーソスの解釈がかけ離れているので終盤は同意できなかった。まず第一に、日本を英米と比較してペーソスに頼っていることを批判するけれども、実はアメリカこそペーソスの拠点で、オー・ヘンリー、広い意味でのブルース、Netflixの傑作シリーズ『コミンスキー・メソッド』、いずれもペーソスが主役である。2021/10/09