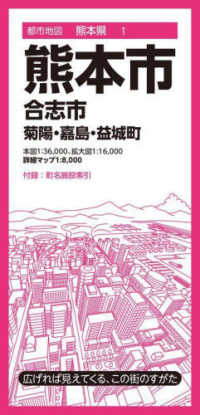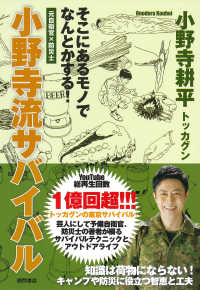出版社内容情報
【担当編集ノート】
上野誠さんといえば、令和の御代の万葉研究を大きくリードする人です。しかし、研究者としてではなく、個人としての上野さんは兄上亡きあとに故郷福岡の一族のお墓をしまい、老いた母上を奈良に呼び寄せて7年のあいだ介護し、見送った家長であり息子でありました。
上野さんの研究において重要かつ本質をなすのは、「宴」についてと「挽歌」についてのそれであると私は考えています。私生活と研究は別のものではありますが、それでも「私」のない研究はありえないと、編集者としての私は考えており、本書はその意味において企画されたものであります。
「はじめに」において上野さんは次のように語ります。
「これから私が語ろうとすることは、個人的体験記でもなければ、民俗誌でもない。評論でもないし、ましていわんや小説でもない。ひとりの古典学徒が体験した、死をめぐる儀礼や墓にたいする考察である。/いや、考察と呼ぶのもおこがましい。私の祖父が死んだ一九七三(昭和四十八)年夏から、母が死んだ二〇一六(平成二十八)年冬の四十三年間の、私自身の死と墓をめぐる体験を、心性の歴史として語ってみたいと思うのである。
(中略)/ 四十三年間という時が歴史になるのか。個人の経験や思いなどを、いったいどうやって検証するのか。それがいったいなにに役立つのかなどという批判は、すでに予想されるところではあるけれども、私はあえて、この方法を世に問いたい、と思う」
そして「あとがき」ではこう言います。「七年間母親を介護し、家じまいをした私は、家族とその歴史に思いを馳せた。そんなときに執筆を思い立ったのが、この本である。/己れが経験した家族の死の体験を、いまの自分の感覚で描いてみたい。己れを始発点とする民俗誌、家族小史のようなものを書いてみたい。それこそ、まぎれもなき実感できる歴史なのではないか。なにも、偉人の伝記をつなぐことだけが歴史でもなかろう、との思いが、ペンを走らせたのである」
いま、墓じまいや「終活」が多くの人の問題となっています。万葉の時代から現代まで、人は誰かを送り、「いずれはわれも」と感じてきました。軽妙な筆ながらその長い営みに思いを馳せた深いエッセイをお届けします。
内容説明
現代万葉研究を大きくリードする学者は、故郷福岡の墓をしまい老いた母を呼び寄せ、七年のあいだ介護して見送った息子でもあった…。体験と学問を軽妙な筆致で往来し、死について深く考えた、真の「エッセイ」。
目次
死の手触り(一九七三年八月十六日;葬式の「格」 ほか)
墓じまい前後(こげな立派な墓はなかばい;墓作りは長崎に学べ ほか)
死にたまふ母(兄のことば;三ヵ月ルール ほか)
われもまた逝く(柳田國男いわく;竹林の七賢と大伴旅人 ほか)
著者等紹介
上野誠[ウエノマコト]
1960年福岡県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学。博士(文学)。現在、奈良大学文学部教授(国文学科)。研究テーマは、万葉挽歌の史的研究と万葉文化論。第12回日本民族学会研究奨励賞、第15回上代文学会賞受賞。『魂の古代学―問いつづける折口信夫』(新潮選書、第7回角川財団学芸賞受賞。『折口信夫 魂の古代学』と改題、角川ソフィア文庫)ほか著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
trazom
こばまり
油すまし
はる
-

- 和書
- 臨床試験の事典
-
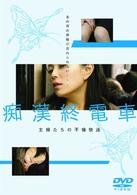
- DVD
- 痴漢終電車 主婦たちの不倫快速