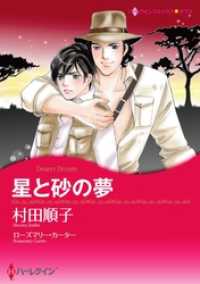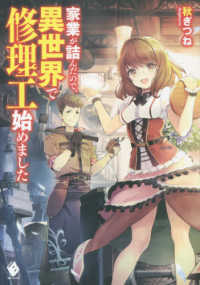出版社内容情報
プラトンによれば、ソクラテスは、「……とは何か」と問うた。「正義とは何か」「美とはなにか」。真理を捉えるための「知性」や「理性」を最も重要な心の働きとする西洋哲学の伝統が、ここから生まれた。
これに対して、本書は、「想像力」を優位におく思想に着目する。イギリスのロマン主義者からはじまって、アメリカのエマーソンに継承され、ニーチェ、ハイデッガー、ローティにつながる系譜である。
真理は定まっていて、「理性」や「知性」は、それをあるがままに捉える能力だとするのが、プラトン的「理性主義」だとすれば、「想像力」とは、新たな見方、捉え方を創造する力である。これをローティは、「詩としての哲学」と呼んだ。
デカルト、カントなど、理性主義の変遷をも検証しつつ、「詩としての哲学」の可能性を問う力作。
内容説明
人間の「理性」「知性」を最も重要な心の働きとする、プラトン以来の西洋哲学における真理探究型の思考。一方、イギリス・ロマン主義から始まり、「想像力」をすべての思考の根本と捉えるエマソン~ニーチェ~ハイデッガー~ローティへの思想の流れ。真理への接近を図る哲学から、開かれた思考を目指す哲学へ、理性主義の系譜を検証し、創造への新たな可能性を探る。
目次
第1部 決別(プラトンとの決別―理性に対する想像力の優位;エマソンとニーチェ―反プラトン主義と新たな円;ハイデッガーの二面性―「思索」と「存在」)
第2部 理由(プラトン的真理観は、どうして機能しないのか―クワイン=デイヴィドソンの言語哲学の観点から;原型的経験論に対する二つの誤解―感覚与件の神話と、ロックに見られる創造的人間観)
第3部 仮説(デカルト―仮説ベースの基礎づけ主義;カント―見せかけの中立性と知の硬直化)
詩としての哲学―桎梏からの解放
著者等紹介
冨田恭彦[トミダヤスヒコ]
1952年、香川県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程研究指導認定退学。博士(文学)。京都教育大学助教授、ハーバード大学客員研究員、京都大学教授を経て、京都大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
シッダ@涅槃
呼戯人
フリウリ
袖崎いたる