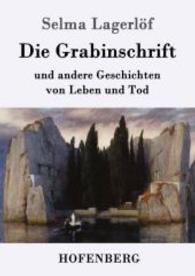内容説明
夫婦関係、親子関係がよくなるコツとは?職場の上司・部下とは、どうすればうまくコミュニケーションがとれるのか?当事者と周囲の人々の「生きづらさ」をなくすためのヒント。
目次
第1章 発達障害とカサンドラ症候群
第2章 職場と人間関係―上司や部下がASDの場合
第3章 家庭と人間関係―家族の誰かがASDの場合
第4章 発達障害と夫婦関係
第5章 発達障害と親子関係
第6章 どうすればラクになれるのか
巻末資料 ASD、ADHDチェックリスト
著者等紹介
宮尾益知[ミヤオマストモ]
東京都生まれ。徳島大学医学部卒業後、東京大学医学部小児科学教室、自治医科大学小児科学教室、ハーバード大学神経科、国立成育医療研究センターこころの診療部発達心理科などを経て、2014年に「どんぐり発達クリニック」を開院。専門は発達行動小児科学、小児精神神経学、神経生理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
71
もやもやした気持ちや状態に名前を付けて具体的な「言葉」にすることで安心と解決をもたらしてくれる本▽ASD=自閉症スペクトラム障害/コミニュケーションや興味、こだわりについて特異性が認められる発達障害。知的障害を伴わない大人のASDも多い。カサンドラ症候群=ASDパートナーと情緒的な相互関係が築けないために、その相手に生じる身体的・精神的症状を表す言葉▽ASDが悪いのでは無い。知ることで対処できることがある。解決の選択肢は一つだけではない。「理解」することが救いになる。「つぶやき作戦」は有効▽わかる。良本2023/04/22
ネギっ子gen
59
発達障害の人と周囲の人たちとが「なんだか違う」に端を発した、剣呑な関係になっている状況からの脱却を願い、発達障害臨床の一人者が、具体的な臨床例を参考にしながら「カサンドラ症候群」を補助線とし、当事者と周囲の人々の「生きづらさ」や「しんどさ」をなくすことを目指した本。発達障害の人と周囲の人との関係性やコミュニケーションに着目しているのが、大きな特長。巻末に、ASDとADHDのチェックリストあり。<自分、また相手にはどのような特性があるかを知っておくのは、良い関係を築き上げていくためにも大事なことです>と。⇒2023/07/16
zag2
30
発達障害について考えてみたいということで、まず一冊。この本は発達障害全般について触れながらも、発達障害でも特にASDの特徴を持つ人の関係者、夫がASDならその妻や、会社の上司がASDであればその部下など、ASDの人と関係を持つ人がカサンドラ症候群になってしまう危険性を述べ、そうならないための心構えなどに言及しています。カサンドラ症候群、初めて聞きましたが、自分の会社人生の中では思い当たることがいくつかあります。たいへん参考になりました。2022/02/21
morinokazedayori
27
★★★★★発達特性を持つ本人と周囲の人のみならず、家庭や職場、また社会全体で特性を理解して対応力を高めていくことが、誰にとってもよい結果をもたらすのではと強く感じた。家庭内でカサンドラになる具体例が非常に詳細に書かれているところが、とても秀逸。カサンドラに関わる全ての人がこれだけの知識を持っているだけでも、当事者は物凄く救われ、回復への一歩となるだろう。2022/07/17
ta_chanko
16
発達障害と定型発達は二分できるものではなく、スペクトラム状につながっている。だから誰にでも、どの家庭にも当てはまるコミュニケーションの問題。一般的に女性は共感を求め、男性は問題解決を考えるのですれ違いが生じやすい。ASDの場合はそれが顕著に現れやすいということ。日常的かつ難しい問題であるが、その原因を知識として理解した上で、日々の言動に気を付けていく他ない。また、他人を変えるのは困難なので、自分から変わっていくことも大切。2021/06/26
-

- 洋書
- Geraçã…