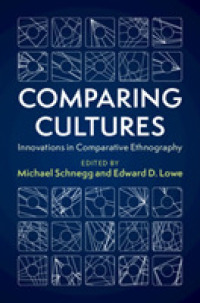内容説明
高山樗牛、宮沢賢治らの心をとらえ、石原莞爾や血盟団の行動を促した日蓮主義とはいかなるものだったのか?帝国日本の勃興期に「一切に亘る指導原理」を提示し、国家と社会と宗教のあるべき姿(仏教的政教一致)を鼓吹した二大イデオローグ=田中智学と本多日生の思想と軌跡を辿り、それに続いた者たちが構想し、この地上に実現しようと奮闘したさまざまな夢=仏国土の姿を検証する。現代日本にまで伏流する思想水脈を問う大著。
目次
近代日本と日蓮主義
田中智学と日蓮主義の誕生
本多日生の積極的統一主義
高山樗牛の日蓮論
仏教的政教一致のプログラム
「修養」としての日蓮主義
「日蓮主義の黄金時代」と日本国体学
石原莞爾と宮沢賢治、そして妹尾義郎
立正大師諡号宣下と関東大震災
観念性への批判、実践の重視
テロルの宗教的回路
攻撃される日蓮主義者たち
理想はどこに
アジアへ、そして世界へ
焼け跡に仏国土を!
著者等紹介
大谷栄一[オオタニエイイチ]
1968年、東京都生まれ。東洋大学大学院社会学研究科社会学専攻博士後期課程修了。博士(社会学)。国際宗教研究所研究員、南山宗教文化研究所研究員を経て、佛教大学社会学部教授。専攻は宗教社会学・近現代日本宗教史。明治期以降の「近代仏教」の展開や、近現代の宗教者や宗教団体がおこなう社会活動・政治活動、「地域社会と宗教文化」の関係を研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
64
日蓮主義というと「国柱会」というその名称や血盟団との関係、石原莞爾に与えた影響などから、漠然と戦前の国家主義を奉ずる一団体というイメージがあった。本書は田中智学がそれを唱えてから全盛期、軍部による弾圧から戦後に至るまでといった流れを詳しく解説し、その漠としたイメージに形を与えてくれた気がする。ただ全体的に日蓮主義の中でも様々な動きがある事は理解できたが、その主義故に戦前の国体と不離にあったのも事実。戦後それが解体されたことにより、その役割を終えたのかな。宗教とナショナリズムを考える上で面白い一冊でした。2022/12/06
ゲオルギオ・ハーン
24
『日蓮主義』という日蓮の考えを宗教だけでなく生活全てにも広げ、社会的には全体を統一する思想として展開していく様子を思想の中心人物の動向、社会の動きも関連させながら考察した一冊。石原莞爾、宮沢賢治、佐藤鉄太郎などの有名人物も関わっている。内容的に本田日召、高山樗牛、田中智学に紙幅を割いており、やはり日蓮宗とは異色なところが多いので日蓮主義と日蓮宗は似て非なるもの、と思いました。どちらかというと、全体主義思想に近いのかな。井上日召の血盟団事件によりテロリズムのレッテルが貼られると衰退していったそうです。2023/05/26
しんすけ
23
不思議なタイトルの本だと思う。 「なんだったのか」とするのは、現在では日蓮主義はもう存在しない、そう言うことなのだろうか。 日蓮宗を騙って法華経を汚すカルトは、まだ存在していると思えるのだが。 著者は、日蓮の真意をくみ取ろうとした時代が、かっては有ったと言いたかったのかもしれない。 しかし、本書を読むと日蓮主義とは狂人の雄たけびだったのでないかと思う。 田中智学から始まった八紘一宇の精神で世界統一を言うまでは良いのだが、それは日本の役割だと言い出し始めると当たり前の神経では付いていけなくなる。2022/11/11
さえきかずひこ
13
近代仏教運動としての日蓮主義の多様なあり方を田中智学、妹尾義郎、石原莞爾を中心としたテクストの考察を通して論じた、明晰な構成ときわめて平易な文体が特徴的な読みごたえのある研究書。西山茂、末木文美士、筒井清忠、原武史らの先行研究を豊富に参照し、現実の日本社会を維持強化する特殊主義的側面とそれを変革していこうとする普遍主義的側面が、日蓮主義の運動としてのダイナミズムを駆動していたことを浮き彫りにする。個人と信仰、そして近代日本のナショナリズムの関係について関心のある方にはとても刺激的な作品だと思います。ぜひ!2020/03/22
Toska
11
祭政一致、戦闘的な折伏志向、日本を中心とする世界統一のビジョン、独特の国体論等々、強烈だなあと思いながら読んでいたら、最後の最後で「日蓮主義は否定的にステレオタイプ化されてきたが、実は…」というような話が出てきたので吃驚。そんな趣旨だったの?日蓮主義についてはそもそも「通説」を云々できるほど一般に知られてもおらず、まずはそこから始めるべきなのでは。例えばウィキペディアで石原莞爾の項目を見ても、日蓮主義の影響はついでにしか触れられていない印象を受ける。2023/09/23