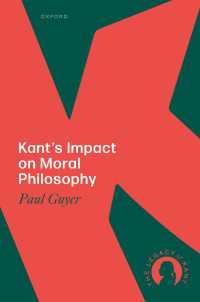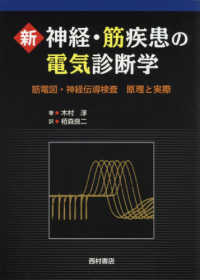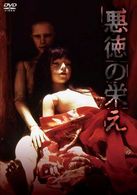出版社内容情報
鈴木 勇一郎[スズキ ユウイチロウ]
著・文・その他
内容説明
「阪急や阪神、東急や西武といった“電鉄”が、衛生的で健全な“田園都市”を郊外につくりあげた」―よく知られたこの私鉄をめぐる物語の深層には、「神社仏閣」を舞台とする語られざる歴史があった。近代の荒波を生き抜く希望を鉄道に見いだした社寺と、そこに成功栄達の機を嗅ぎつける怪しくも逞しき人々。彼らの無軌道な行動と激しい情熱こそが、この国の都市空間をつくったのだ!ダイナミックで滑稽で、そして儚い、無二の日本近代都市形成史。
目次
序章 「電鉄」はいかにして生まれたか
第1章 凄腕住職たちの群像―新勝寺と成田の鉄道
第2章 寺門興隆と名所開発―川崎大師平間寺と京浜電鉄
第3章 「桁外れの奇漢」がつくった東京―穴守稲荷神社と京浜電鉄
第4章 金儲けは電車に限る―池上本門寺と池上電気鉄道
第5章 葬式電車出発進行―寺院墓地問題と電鉄
終章 日本近代都市と電鉄のゆくえ
著者等紹介
鈴木勇一郎[スズキユウイチロウ]
1972年、和歌山県生まれ。青山学院大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(歴史学)。専攻は日本近代史、近代都市史。現在、川崎市市民ミュージアム学芸員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Roko
28
初期の鉄道敷設計画は、成田山(成田電鉄)、川崎大師(京浜電鉄)、穴守稲荷神社(京急電鉄)、池上本門寺(池上電気鉄道)など、いずれもお寺や神社へ電車で行けるようにすれば、参詣者が増えるという目論見から生まれたのです。つまり、寺や神社側の依頼によって作られたものなのです。 それ以外にも様々な人が電車を使うことで新しいビジネスを起こそうと考えたのです。競馬場や遊興施設、温泉、三業地、そして墓地まで。2022/10/12
onasu
22
大都市から郊外へ延びる私鉄とは、沿線住民の通勤、通学の足であってとは、現状ではその存在の第一義だが、それらの敷設された経緯を掘り起こしていくと、思わぬ歴史が埋もれていた。 まずもって、都市の人口が増えて郊外が必要になったのは大正の半ば過ぎだが、各線の敷設計画は明治の終わり頃から始まるのだから、当初の目的はそうじゃなかった。 答えとしては、表題と共に成田山新勝寺や川崎大師と挙げていけば明白で、そこには銭勘定に長けた坊主や歴史に埋もれた怪物も…。 寺の記述の多いのには辟易したが、興味深い一冊でした。2019/06/20
seki
11
首都圏の大手私鉄の成り立ちが主に書かれた本。京急、京浜といった名だたる私鉄が、明治、大正期に、参詣客の増を狙う寺社仏閣のやり手の僧侶たちと結びつき、参詣鉄道として出発したというのがメインの話。阪急のように、私鉄は住宅地や遊興施設の開発をセットにした経営モデルというイメージを払拭しようというのが筆者の意図らしい。国鉄・JRと私鉄の役割の違いがいまいち分からなかった自分には、目からウロコの内容が盛りだくさんだった。ほかに葬式列車の話も。当時の都市計画の問題も垣間見れて、とても面白い一冊だった。2019/09/15
hitotak
10
戦前の私鉄敷設には寺社仏閣の参拝客を運ぶという目的があったというのは新しい視点で、面白く読んだ。江戸期に人気だった寺院も廃仏毀釈の影響で財政が苦しくなる所も出てきたが、川崎大師、成田山新勝寺に大勢の参拝客が訪れ、門前町も潤うようになったのは仕掛け人の凄腕住職がいたからだとか。ビジネス才覚の有無と地の利が命運を分けたのだろう。初詣という行事が始まったのも明治20年位からで、現在も関東圏で1、2を争う参拝客がこの2寺院に集まるのも両寺の努力の結果と言えるのではないか、と述べられている。2019/09/08
アメヲトコ
10
田園郊外の住宅地開発という小林一三モデルで語られがちな近代の私鉄史に異議を唱え、その前段階にあった社寺参詣との関係にスポットを当てた一冊。成田山や川崎大師、穴守稲荷に池上本門寺といった事例はまあそうだろうなと思いつつ読んだのですが、面白かったのは最後の葬式電車の章。とくに北大阪電鉄(現阪急千里線)の初期構想と墓地開発の関係などはなるほどと目を啓かれました。2019/05/31