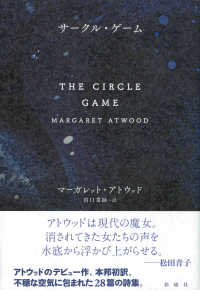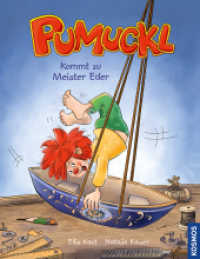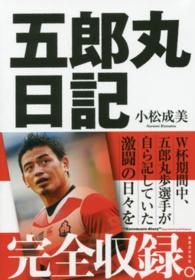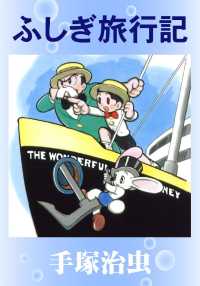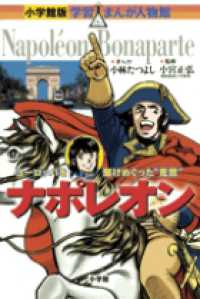出版社内容情報
他者と祖先と自らの死の翳を見つめながら綴られる日々の思索と想念。80歳を過ぎ、ますます勁健な筆を奮う、古井文学の真骨頂!祖先、肉親、自らの死の翳を見つめながら、綴られる日々の思索と想念。死を生の内に、いにしえを現在に呼び戻す、幻視と想像力の結晶。80歳を過ぎてますます勁健な筆を奮い、文学の可能性を極限まで拡げつづける古井文学の極点。
たなごころ
梅雨のおとずれ
その日のうちに
野の末
この道
花の咲く頃には
雨の果てから
行方知れず
古井 由吉[フルイ ヨシキチ]
著・文・その他
内容説明
個の記憶を超え、言葉の淵源から見晴るかす、前人未踏の境。待望の最新小説。
著者等紹介
古井由吉[フルイヨシキチ]
1937年東京生まれ。東京大学大学院修士課程修了。71年「杳子」で芥川賞、80年『栖』で日本文学大賞、83年『槿』で谷崎潤一郎賞、87年「中山坂」で川端康成文学賞、90年『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
77
80歳を過ぎた作家の感性が響く。その日の天気に体をまかせ、日々の出来事に想いをめぐらし、死と向かい合い、戦時中の記憶が蘇り、それでも生きている毎日。自分よりも、まだまだ年長の作家だが、その心の描写に、なぜか引き込まれてしまう。老いとは辛いものだが、この豊かな感性は、若者には描けないと思った。2019/05/03
クリママ
48
日比谷高校の同級生に塩野七生と福田章二がいるとウィキにあるが、古井由吉は初読みである。つれづれなるままに書かれたような随筆。徒然草はおもに説話の形をとっているのに対し、この作品はまとまった何かというより、過去や現在に行きつ戻りつ移ろい、老いを悲しむようであり、達観しているようでもあり。「その日のうちに」の後半部分に老人を送っていく少し長めの場面があり、それはまさにその情景を見、心情を重ねることができる。この作家の作品はそのようなのだろうか。高尚な(それ以外に何と言っていいかわからない)日本語であった。2019/06/27
クプクプ
42
最高に面白かったです。「杳子・妻隠」の頃より、さらに磨きがかかっています。夏目漱石の「草枕」をもっとよくして成功したような作品でした。私はエッセイだと思いました。「草枕」のように対象を飾っていく文体ですが自然な仕上がりがよかったです。内容は最近の出来事なので読みやすいと思います。最後は最寄り駅のホームのベンチで読みましたが、いい本はコーヒーやごちそうにも勝ると感じました。特に読書力のある方が揃う読書メーター向きの本だと思いました。2019/04/09
踊る猫
33
既に提示したモチーフを、自己模倣を恐れることなく更に上書きして、そこから発展させていく。平たく言えば新しいことはなにもやっておらず、ただ過去にやったことをなぞっている。だから変化はない。その代わり、恐ろしいほどの勢いで円熟していると感じさせる。そして、この円熟と枯淡の境地を受け継げる作家は確かに少ないだろうなと思うし、ましてこの域まで大胆にゴーイングマイウェイに続けられた作家も居ないだろうな、と思うのである。時代と無縁の場所でブンガクし続けているようで、実は風俗や文化の変化を意識した書き手がここに君臨する2019/12/25
かんやん
32
今年二月逝去された著者の昨年刊行された短編集。長年愛読してきた作家の、脈絡のあるような、ないような、それでも慣れ親しんだ身辺雑記と随筆風の文章を辿ってゆくと、このエピソードはあの短編にもあった、あの引用はあの作品集にもあったといった具合に思い出せるし、人生の段階も、居所もすっかり頭に入ってることに今さら驚きもしない。マンネリだとか、ネタ不足とか、繰り言と捉える向きもあろうが、ファンとしては何度でも味わい深い、実に興趣に富む。この年までやはり飽きもせずに読んできたし、これからも又読み返すのだろうな、と。2020/10/15