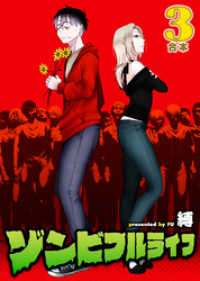- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 講談社ブルーバックス
出版社内容情報
なぜ音楽は音をデジタル化し、ドレミ…を使うことにしたのか? なぜ特定の和音は心地よいのか? 簡単な数学で音楽の秘密をあばく!モーツァルトからピンク・レディーまで 名曲の陰に数学あり!
・科学の眼で見る音楽と楽器
本書は、科学(おもに数学と物理学)の眼から見える音楽と楽器のあらたな一面を紹介するものです。およそ10年前に発売され20回以上増刷してきた人気作が、新たな内容を加え、装いを新たに生まれ変わりました!
・本書の構成
第1章 ドレミ…を視る,ドレミ…に触れる
第2章 ドレミ…はピタゴラスから始まった
第3章 音律の推移――閉じない環をめぐって
第4章 なぜドレミ…が好き?――音楽の心理と物理
第5章 コードとコード進行――和音がつくる地形を歩く
第6章 テトラコルド――自由で適当な民族音楽
第7章 楽器の個性を生かそう
第8章 音律と音階の冒険――新しい音楽を求めて
・音楽と数学
音楽はドレミ…という決まった音を使います。音とは空気の振動であり、わたしたちはその振動数のちがいを音高のちがいとして聞き取ります。音楽が決まった音(周波数)を使うということは、逆に言えば、それ以外の周波数の音を使えないということです。ドとレの間に音は無限に存在する(周波数を細かく区別できれば、無限の音を扱える)のに、音楽で使えるのはド♯(あるいはレ♭)だけ……。
音楽は音をデジタル化している、とも言えます。ではそのデジタル化はどのようなルールにもとづくのでしょうか? ここに簡単な数学が登場します。ドレミ…に割り当てられた周波数を並べて数列をつくってみると、学校で習った「ある数列」が現れるのです。
・ピタゴラスのおかげ!?
音楽が使う音をデジタル化したのは、紀元前6世紀に活躍したピタゴラスでした(三平方の定理あるいはピタゴラスの定理で有名な、あの方)。彼は楽器を使って音の研究をしていました。ピタゴラスが1オクターブを構成する12音(音律)を決めた実験はシンプルで、私たちも簡単に再現することができます(方法は本書で紹介)。その実験は「心地よい和音」の理解にもつながります。
もちろん、音楽や楽器の進化とともに音律は変化をくり返してきました。しかし、根本のアイデアはピタゴラスから変わることなく生き続けています。世界のあらゆる名曲がピタゴラスのおかげで誕生したのかもしれません。
ドレミ…を視る,ドレミ…に触れる
ドレミ…はピタゴラスから始まった
音律の推移――閉じない環をめぐって
なぜドレミ…が好き?――音楽の心理と物理
コードとコード進行――和音がつくる地形を歩く
テトラコルド――自由で適当な民族音楽
楽器の個性を生かそう
音律と音階の冒険――新しい音楽を求めて
小方 厚[オガタ アツシ]
著・文・その他
内容説明
音楽では特定の高さ(周波数)の音(ドレミ…)しか使えない。なぜそのような不自由な形になったのか?この「不自由さ」が生まれたのは、よりよい音の組み合わせを追求した結果だった!紀元前6世紀のピタゴラス研究から始まる音律の進化をたどり、簡単な数学にもとづく音楽の「心地よさ」の秘密を解き明かす。
目次
第1章 ドレミ…を視る、ドレミ…に触れる
第2章 ドレミ…はピタゴラスから始まった
第3章 音律の推移―閉じない環をめぐって
第4章 なぜドレミ…が好き?―音楽の心理と物理
第5章 コードとコード進行―和音がつくる地形を歩く
第6章 テトラコルド―自由で適当な民族音楽
第7章 楽器の個性を生かそう
第8章 音律と音階の冒険―新しい音楽を求めて
著者等紹介
小方厚[オガタアツシ]
1941年東京生まれ。名古屋大学プラズマ研究所(現・核融合科学研究所)、日本原子力研究所(現・日本原子力開発機構)、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、広島大学を経て、KEK名誉教授。専門はビーム物理(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
COSMOS本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
skunk_c
Tenouji
魚京童!
にしがき