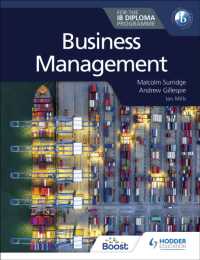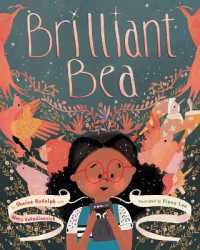出版社内容情報
中世は、決して暗黒期ではない。中世とルネサンスの間に、断絶はない――。中世の歴史的位置づけを真っ向から問い直した問題作。中世は、決して暗黒期ではない。中世とルネサンスの間に、断絶はない――。
ルネサンス(古典復興)は1400年代(クァトロチェント)のイタリアで突然起こったのではなく、ヨーロッパ各地でそれに先駆け、すでにさまざまな創造がなされていた。
「中世」というとギリシア・ローマ文化を破壊、封印した陰鬱な時代、と捉えられがちだが、それはまったくの誤解である。とりわけ12世紀頃における文化復興は「中世ルネサンス」と呼ばれ、新鮮な活力にあふれている。
ラテンの古典と詩が息を吹き返し、遊歴詩人たちから聖俗混ざった抒情詩『カルミナ・ブラーナ』が生まれる。ローマ法の復権が見られ、ギリシアをはじめアラビア、スペイン、シチリア、シリア、アフリカと多方面から知識が流れ込み、それは哲学、科学の発展をもたらした。そして七自由学芸(リベラル・アーツ)のさらなる充実、知識の膨張による、必然としての大学の誕生……
「他に例を見ないほど創造的な、造形的な時代」(ホイジンガ)の実像をたどり、中世の歴史的位置づけを真っ向から問い直した問題作。アメリカの中世史家はこの大著で歴史的転換を迫り、従来の暗黒史観に衝撃を与えた。
(C.H.Haskins,The Renaissance of the Twelfth Century,Harvard University Press,1927.邦訳『十二世紀ルネサンス』みすず書房、1989初版、1997新装)
はしがき
第一章 歴史的背景
第二章 知的中心地
第三章 書物と書庫
第四章 ラテン語古典の復活
第五章 ラテン語
第六章 ラテン語の詩
第七章 法学の復活
第八章 歴史の著述
第九章 ギリシア語・アラビア語からの翻訳
第十章 科学の復興
第十一章 哲学の復興
第十二章 大学の起源
原注
解説(朝倉)
あとがき(別宮)
文献書誌
チャールズ.ホーマー・ハスキンズ[チャールズ.ホーマー ハスキンズ]
著・文・その他
別宮 貞徳[ベック サダノリ]
翻訳
朝倉 文市[アサクラ ブンイチ]
翻訳
内容説明
イタリア・ルネサンス以前、十二世紀の西欧ではすでに知的復興が行われ、活き活きと文化が華開いていた。ローマ古典の再発見、新しい法学、アラビアの先進知識との遭遇、大学の誕生。「封建的で陰惨な断絶された時代」という中世の理解は正しいのか―精緻な写本研究と文献学の成果で西洋史に新たな枠組みを提示し、今も指標とされる不朽の名著。
目次
歴史的背景
知的中心地
書物と書庫
ラテン語古典の復活
ラテン語
ラテン語の詩
法学の復活
歴史の著述
ギリシア語・アラビア語からの翻訳
科学の復興
哲学の復興
大学の起源
著者等紹介
ハスキンズ,チャールズ・ホーマー[ハスキンズ,チャールズホーマー] [Haskins,Charles Homer]
1870‐1937。アメリカの歴史家。ハーヴァード大学教授
別宮貞徳[ベックサダノリ]
1927‐。英文学、比較文学。元上智大学教授
朝倉文市[アサクラブンイチ]
1935‐。西洋中世史。ノートルダム清心女子大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。