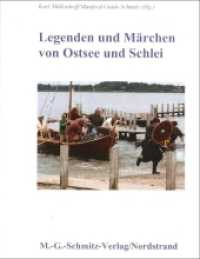出版社内容情報
「精神分裂病」は何が「分裂する」というのか、どんな病態なのか。これまでの誤謬を論破し、治療へつながる「病の本質」を解明する。昏迷・妄想・幻聴・視覚変容……これらの症状は何に由来するのか。病名の誕生当初から「人格の崩壊」「知情意の分裂」などと理解されてきた謬見が次第に正されつつある。患者はどうして、どんな不具合を抱えているのか。精神科臨床に長年携わってきた著者が、脳研究の成果も参照し、治療につながる病気の本態と人間の奥底に蠢く「原基的なもの」を語る。
第一回講義 決まり文句を疑う
第二回講義 精神医学に潜む虚妄
第三回講義 急性期医療と「陰性症状」
第四回講義 現実と妄想
第五回講義 妄想の発生と由来
第六回講義 運動が阻害されるということ
第七回講義 取り憑かれるということ
第八回講義 「自我」「自分」「主体」「自己」
第九回講義 何が分裂し、何が統合されるのか
計見 一雄[ケンミ カズオ]
著・文・その他
内容説明
昏迷・妄想・幻聴・視覚変容…これらの症状は何に由来するのか。病名の誕生当初から「人格の崩壊」「知情意の分裂」などと理解されてきた謬見が次第に正されつつある。患者はどうして、どんな不具合を抱えているのか。精神科臨床に長年携わってきた著者が、脳研究の成果も参照し、治療につながる病の本態と人間の奥底に蠢く「原基的なもの」を語る。
目次
第1回講義 決まり文句を疑う
第2回講義 精神医学に潜む虚妄
第3回講義 急性期医療と「陰性症状」
第4回講義 現実と妄想
第5回講義 妄想の発生と由来
第6回講義 運動が阻害されるということ
第7回講義 取り憑かれるということ
第8回講義 「自我」「自分」「主体」「自己」
第9回講義 何が分裂し、何が統合されるのか
著者等紹介
計見一雄[ケンミカズオ]
1939年東京生まれ。千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉県精神科医療センターの設立に参画、現在名誉センター長。公徳会佐藤病院顧問。精神科救急医療という分野の開拓者で、日本精神科救急学会前理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どらがあんこ
またの名
雑食奈津子
qbmnk
amanon