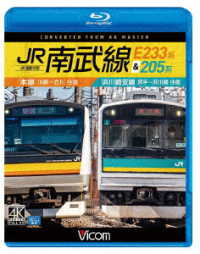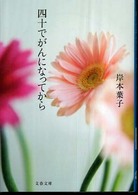出版社内容情報
我が国最大の説話集の、本朝(日本)の世俗説話を収めた、巻二十二?三十一。その平易で読みやすい全現代語訳をコンパクトに刊行。我が国最大の説話集であり、内容の多様さも文学的興趣も群を抜く「今昔物語集」。古来我が国で「世界」を意味した三国、天竺・震旦・本朝(インド・中国・日本)の一千を超える説話を収めた三十一巻(うち三巻を欠き、現存は二十八巻)のうち、本朝の世俗説話を収めた巻二十二?三十一。その平易で読みやすい全現代語訳をコンパクトに刊行。語注も充実。巻二十二?巻二十四。
凡 例
巻第二十二 本朝
巻第二十三 本朝
巻第二十四 本朝 付世俗
巻第二十五 本朝 付世俗
巻第二十六 本朝 付宿報
解 説 武石彰夫
参考付図・系図
武石 彰夫[タケイシ アキオ]
翻訳
内容説明
全三十一巻、千話以上を集めた日本最大の説話集。本朝(日本)に対し、天竺(インド)・震旦(中国)という、当時知られた世界全域を仏教文化圏として視野に置く。本巻にはこのうち本朝の世俗説話の前半、巻第二十二~二十六を収めた。藤原氏の来歴、転換期に新しく立ち現れた武士の価値観と行動力、激動を生き抜く強さへの驚嘆と共感を語り伝える。
目次
大織冠、始めて藤原の姓を賜れる語、第一
淡海公を継げる四家の語、第二
房前の大臣、北家を始めたる語、第三
内麿の大臣、悪馬に乗りたる語、第四
閑院の冬嗣の右大臣ならびに息子の語、第五
堀河の太政大臣基経の語、第六
高藤の内大臣の語、第七
時平の大臣、国経大納言の妻を取る語、第八
平維衡同じき致頼、合戦して咎を蒙る語、第十三
左衛門尉平致経、明尊僧正を導く語、第十四〔ほか〕
著者等紹介
武石彰夫[タケイシアキオ]
1929‐2011。東京都生まれ。国文学者。専門は仏教歌謡。法政大学文学部日本文学科卒業。文学博士。高知大学教授。仏教文化研究所長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
テツ
きょちょ
fseigojp
たまきら