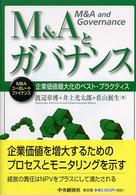出版社内容情報
「いれずみ」ではなく「しせい」。それはいかに芸術となったか。異端美の系譜を追求し続けた著者による、日本刺青の精神史。刺青、それは閉ざされた美である。暗黒のゆえに極彩の美である。秘めよ、秘められよ、開かれてはならない。いつの日にも俗物への、体制への、衝撃であらねばならない――。生命に彫り込まれた虚構、解脱を拒否した無頼の詩語。それはいかにして芸術に高まったのか。異端と抵抗の系譜を追究し続けた著者による、日本刺青の精神史。
*
本書の題名は、「刺青(しせい)・性(せい)・死(し)」と読んでほしい。刺青を「いれずみ」とは読んでほしくない。いうまでもなく、「いれずみ」は近世における法制用語である。――「あとがき」より
【刺青】
一 刺青への誘い
二 刺青・その秘匿と顕示
三 革命と聖痕
【性】
一 痛みと怨恨の機能
二 南北復活における血の論理
三 絵金神話の詩と真実
四 戯画としてのユートピア
【死】
一 一人による犠牲死
二 性と死の冥婚
(解説 平井倫行)
松田 修[マツダ オサム]
著・文・その他
内容説明
刺青、それは閉ざされた美である。暗黒のゆえに極彩の美である。秘めよ、秘められよ、開かれてはならない。いつの日にも俗物への、体制への、衝撃であらねばならない―。生命に彫り込まれた虚構、解脱を拒否した無頼の詩語。それはいかにして芸術にまで高まったのか。異端美の系譜を追究し続けた著者による、日本刺青の精神史。
目次
刺青(刺青への誘い;刺青・その秘匿と顕示;革命と聖痕―田中英光における「神」なるもの)
性(痛みと怨恨の機能;南北復活における血の論理;絵金神話の詩と真実;戯画としてのユートピア―『曼陀羅』におけるエスノロジー)
死(一人による犠牲死;性と死の冥婚)
著者等紹介
松田修[マツダオサム]
1927年生まれ。京都大学国文学科卒業。法政大学教授などを経て、国文学研究資料館名誉教授。専攻は日本近世文学・日本芸能史。異端的視覚をもって近世文化の陰闇に切り込み、美の様式をあらわした。日本の刺青研究の第一人者としても知られる。2004年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
磯良
ankowakoshian11
ygreko