出版社内容情報
東京が生まれた! 江戸から大震災まで、モダン都市〈東京〉への変貌をたどる原・東京の旅。米国人による東京論、日本文化論の名著。
〈東京〉は、いつ生まれ、どう育ったのか。
江戸の残照を映す下町と、下町文化。
近代化を担った山の手と、山の手文化。
二つのせめぎあいと融けあいを軸として、
1867年から1923年まで―明治維新から関東大震災まで――モダン都市・東京へと変貌するさまをたどり、
江戸の香りが失われてゆく〈原・東京〉の姿を愛惜をこめて描く。
谷崎潤一郎、川端康成、永井荷風、三島由紀夫らを英訳し、源氏物語の英訳を完成させるなど数々の日本文学を世界に紹介した泰斗による東京論・近代日本論の名著。
はしがき
1 終末、そして発端
2 文明開化
3 二重生活
4 デカダンスの退廃
5 下町 山の手
6 大正ルック
訳者あとがき
【著者紹介】
1921~2006年、アメリカ・コロラド州生まれ。海軍日本語学校で日本語を学び、海兵隊員として日本に進駐。コロンビア大学で修士号を取得したのち国務省に勤務。1947~50年に外交官として滞日中、東京大学にて日本文学を専攻。日本文学を講じてコロンビア大学教授などを歴任した。谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫らの作品を英訳し、1975年には『源氏物語』を英訳を完成させる。2006年、日本に永住すべく東京・湯島を生活の拠点としたが、翌年に死去。
○主な著書:
『現代日本作家論』佐伯彰一訳、1964年。
『異形の小説』安西徹雄編訳、1972年。
『湯島の宿にて』安西徹雄訳、1976年。
『源氏日記』安西徹雄訳、1980年。
『日本人とアメリカ人』海老根宏編注、1978年。
『私のニッポン日記』安西徹雄訳、1982年。
『流れゆく日々 サイデンステッカー自伝』安西徹雄訳、2004年。『谷中、花と墓地』2008年。
○主な英訳書:
『蜻蛉日記』『細雪』『雪国』『伊豆の踊り子』『美しい日本の私』『山の音』『源氏物語』など。
内容説明
“東京”は、いつ生まれ、どう育ったのか。本書は数々の日本文学を世界に紹介した泰斗による東京論・近代日本論である。江戸の残照を映す下町と、下町文化。近代化を担った山の手と、山の手文化。二つのせめぎあいと融けあいを軸としながら、維新から大震災まで、モダン都市・東京へと変貌するさまをたどり、失われゆく“原・東京”を愛惜をこめて描く。
目次
1 終末、そして発端
2 文明開化
3 二重生活
4 デカダンスの退廃
5 下町 山の手
6 大正ルック
著者等紹介
サイデンステッカー,エドワード・G.[サイデンステッカー,エドワードG.] [Seidensticker,Edward G.]
1921~2007年。米コロラド州生まれ。コロンビア大学教授などを歴任
安西徹雄[アンザイテツオ]
1933~2008。松山市生まれ。上智大学名誉教授。専攻は英文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わんつーろっく
ハチアカデミー
本の蟲
yooou
hitotak
-
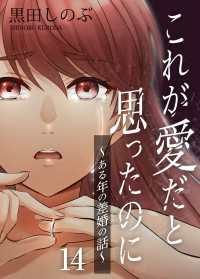
- 電子書籍
- これが愛だと思ったのに~ある年の差婚の…
-
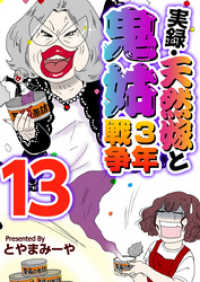
- 電子書籍
- 実録・天然嫁と鬼姑3年戦争 13巻 T…







