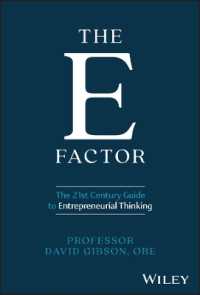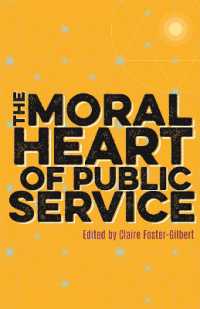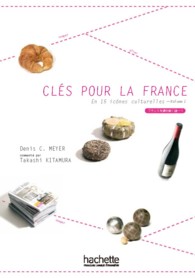出版社内容情報
「遊び」から見える「元禄町人文化」の深層江戸太平の世、町人たちの担う都市大衆文化が豊かに花開いた。多様な芸事、悪所と呼ばれた遊里、人々を熱狂させた芝居。「遊び」の視点から活写する元禄文化史。
内容説明
十七世紀末、元禄文化が花開く。文学、絵画、工芸のみならず、町人が主役となり、奢侈の風俗を生んだ。遊里に入り浸る新興商人、芸事に溺れ身を滅ぼす二代目、芝居に憂き身をやつす人々。生産と消費の外部にある第三の領域=「遊び」という視点から、太平の世の町人文化の深層に迫る。
目次
序章 「町人」の時代―『日本永代蔵』の世界から
第1章 「遊芸」という行為(ものみな遊芸―遊芸の構図;「外聞」としての遊芸―芸事の機能;遊芸をささえるもの―遊芸の周辺 ほか)
第2章 「悪所」という観念(「悪所」という言葉;遊里批判の論理;虚偽と虚構 ほか)
第3章 「芝居」という空間(「芝居」と芝居見物;「芝居小屋」をめぐって;とざされた「小屋」 ほか)
著者等紹介
守屋毅[モリヤタケシ]
1943~1991。早稲田大学第一文学部卒業。立命館大学大学院文学研究科修士課程修了。日本中世・近世文化史専攻。京都市史編さん所員、愛媛大学助教授、国立民族学博物館教授を歴任。文学博士。1986年、河竹賞、サントリー学芸賞(芸術・文学部門)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
56
江戸太平の華ともいえる元禄の世。その時代の町人文化を遊芸、遊里、芝居という三つのキーワードを元に紐解いていく一冊。正直滅茶苦茶面白く、最初の遊芸の部分から一気に引き込まれていく。何故この時代に遊芸が町人文化として一気に花開いたのかという疑問と、遊芸の持つ教養と破滅の二面性などはまさに教えられる事ばかり。悪所の部分はそれが孕む虚構性と「イエ」と性などの論考は極めて刺激的だし。元禄文化というものが江戸時代に花開いた一時の物ではなく、現在に通じる普遍性を孕んだものとして認識させてくれる本。極めて面白かったです。2020/11/06
bapaksejahtera
19
元禄とそれを前後する時代の民衆の担う都市文化を論述する。経済力を有する民衆は、その財力を限られた方向、即ち書題の遊芸悪所芝居に向けた。その流れは江戸時代を通じて続き、更に今日の文化にも色濃く残る由。詩歌管弦碁将棋等の芸事は、それ迄その蘊奥は秘伝として専業従事者に伝えられ、少数の愛護者に保護されたが、民衆の識字力向上もあり市場化される。その現れが入門書出版と家元制度。遊郭は治安維持もあり公許されたが、それが齎す奢侈の大衆化は危険視され、悪所視される。芝居もそれに類する。役者の男倡としての性格は刺激的である。2025/11/22
出世八五郎
5
元禄元年=1688。遊芸,悪所,芝居の3点について調べてあります。それぞれの原初や性質などに触れるにつれ、その意外性に驚き、現代のキャバクラ好きな男についての理解が深まりますが、学術文庫だけに面白可笑しく書かれてるわけではないので、事実のみを知り『ふ~ん♪へぇ~♪』な本です。いずれにせよ、世界初の大衆文化が生まれたこの時代元禄元年=1688は記憶されるべきと思う。本書は大きめの文字で内容もサラっと読み易く、小難しいものでもなく、おすすめ。
1.3manen
5
幸せは仕合せ、運、才覚(13ページ)。現代日本は占いはじめ、ブータンに影響されたかのような、「幸せ」ブームだが、結局、実力以外に運も大きな要因。蓄財と消費の二律背反(17ページ~)。これは現代に通じるものがある。学術的と思わせる「○○性」が結構出てくる。パターン化したい意図はわかるが、多用されると無味乾燥化していくとも思えた。文化とは、人間の価値観と行動の様式(166ページ)。小市民が大衆文化の誕生を導いたようだ(169ページ)。解説でも、日本市民文化の原点とある(熊倉功夫氏196ページ)。文化の市民性?2012/12/23
saladin
4
生産と消費の枠の外にある第三の領域を”遊び”と名づけ、そこから元禄町人文化の内部を探った著作。そのために用いるのが”遊芸”、”悪所”、”芝居”という3つの視点。解説によると、文化の本質の中にこれらがあるという考えは今現在では当たり前らしく、本著はその嚆矢のようだ。元禄文化論として、全体を大きく把握するのによいだろう。2023/11/21