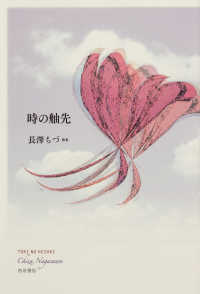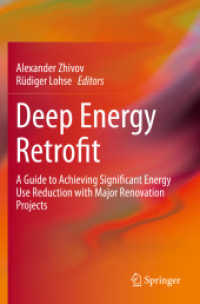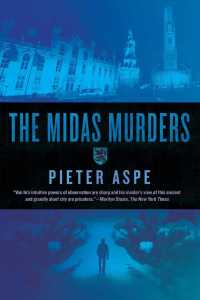内容説明
記紀神話の力くらべ、御前の女相撲、技芸による年占が国家的行事=相撲節へと統合された律令時代。時代を下るにつれ、武芸大会へと変貌し、相撲人は固定化する。寺社祭礼への奉納、武士の娯楽を経て、営利勧進相撲へと発展する江戸期。「国技」として生まれ変わる明治以降。千三百年超の相撲史を総合的に読み直し、多様・国際化する相撲の現在を問う。
目次
序章 相撲の起源
第1章 神事と相撲
第2章 相撲節
第3章 祭礼と相撲
第4章 武家と相撲
第5章 職業相撲の萌芽
第6章 三都相撲集団の成立
第7章 江戸相撲の隆盛
第8章 相撲故実と吉田司家
第9章 近代社会と相撲
第10章 アマチュア相撲の変貌
終章 現代の相撲
著者等紹介
新田一郎[ニッタイチロウ]
1960年生まれ。東京大学文学部卒業。同大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。日本法制史専攻。東京大学相撲部部長。日本学生相撲連盟理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
21
1994年初出。武道必修化で相撲をする学校もあろう。裏表紙には、相撲を「すまい」と読ませている。この呼称は古代に出てきて、中世には普通にすまいと言っていたようだ(28頁)。相撲節(すまいのせち)。相撲人(すまいびと)。野相撲は、中世から近世にかけて、辻や野原で飛び入り勝手の相撲がおこなわれた。秩序を乱すということで、禁止令が出たという(183頁)。鎌倉幕府でも禁止令(190頁)が出ていたので、何年もそうした飛び入り相撲は規制の対象だったのだろう。土俵は17世紀に登場したとみられている(217頁)。2013/11/24
雲をみるひと
13
相撲の歴史を相撲の主催者や相撲取りの立場などを中心に年代順に纏めた本。相撲関係者にも知ってもらいたい内容だが、相撲を知らなくても楽しめる。先史時代から現在に繋がる相撲の流れがわかるし、相撲がなぜ現在の様式で行われているかも感じさせられる。2020/10/31
Toska
12
角界関係者やスポーツジャーナリストではなく、本職の歴史家(ただし大の好角家)が書いた相撲史。例えるなら蕎麦屋が作った絶品カレーの如き深い味わいがある。先行研究や史資料に拠った堅実な内容だが、コラムなどを交えて読みやすくする配慮も。相撲を構成する様々な要素の中でも、「興行」という側面を重視しているのが特徴。実際、相撲は早い段階でプロ集団が現れ、競技者のみならず観戦者をも楽しませるものとなっていった。この点で、弓術や馬術など他の武芸と大きく異なる。2024/09/22
しんさん
7
神事であり異民族支配の象徴であり、芸能、興行であり、大和魂の象徴だったり、スポーツでもあり。「国技」になったのは20世紀になってから。時代によって融通無碍にかたちをかえ、頼る先をかえてきたのが相撲である、と。非常に日本らしいエンターテイメントだなと納得。良本。2022/05/20
ヒロユキ
4
野見宿禰と當麻蹴速による神話の時代から始まった相撲は平安時代に相撲節として宮中行事に定着した。その後京都を中心として奉納相撲を職業とする相撲人集団が形成されるとこれが江戸時代にかけて営利の勧進相撲へと発展する。現代の大相撲は明治時代の国粋主義を背景にこれが国技として体系化されたものである。最後に現代のアマチュア相撲にも触れられる点で、この本は題名通り相撲の通史そのものである。2023/01/11