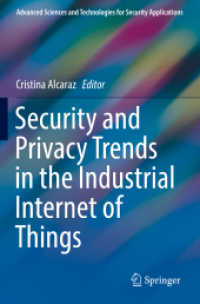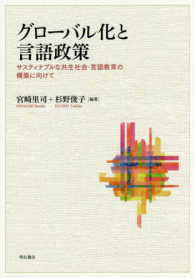出版社内容情報
弥生・古墳時代の実態と王権誕生の謎に迫る 稲作伝来、そして、ムラからクニ、国へ。巨大墳丘墓、銅鐸のマツリ、その役割と意味は何か。王権誕生へのダイナミックな歴史のうねり、列島最大のドラマを描く。
寺沢 薫[テラサワ カオル]
著・文・その他
内容説明
前六世紀末から四世紀末、稲作伝来以来、日本列島は大きく変貌した。弥生人の生活はどのようなものであったのか。各地に残る環濠集落、石剣が突き刺さった人骨、大量に埋納された銅鐸・銅剣、巨大墳丘墓の築造。カミから神へ、マツリから祭りへ、ムラからクニ、国へ。王権誕生・確立までのダイナミックな歴史のドラマを最新の研究成果を結集し描く。
目次
プロローグ 弥生時代とは
第1章 稲作伝来
第2章 コメと日本文化―日本的農業と食生活
第3章 青銅のカミとマツリ
第4章 倭人伝の国々
第5章 情報の争奪と外交
第6章 倭国乱れる―王権への胎動
第7章 王権の誕生
第8章 王権の伸長
エピローグ 世界史と現代へのまなざし
著者等紹介
寺沢薫[テラサワカオル]
1950年東京都生まれ。同志社大学文学部卒。現在、奈良県立橿原考古学研究所総務企画部長。専門は日本考古学で、考古学からの国家形成史、東アジアの農業史、比較文化史をめざす。古代学研究会代表。第15回濱田青陵賞受賞(2002年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
131
面白い。稲作はどこから来たか 邪馬台国、都市の始まり、等に独特の意見を持っているらしく。国家の誕生は前3世紀、弥生時代前期末、という見解も随分早い2025/02/14
KAZOO
111
この第2巻では、弥生時代となり、稲作が伝播し日本の基本的な食生活が定着したころなのでしょう。王権が誕生するまでに結構騒乱があったのですが、この本ではやまとの纒向古墳が中心であったという論をとっています。かなりきめ細かく分析されていて読みでがありました。2017/02/26
南北
46
読み友さん本。日本の「王権」がいつどのように発生したのか、縄文時代晩期から古墳時代前期までの期間にわたって考えようとしている。わずか四半世紀前の本だが、水稲農耕の伝来ルートが朝鮮半島経由している点などは現在では否定されている等、他にも独自の主張がいくつかあるため鵜呑みにはできないと感じた。水稲農耕に関しては分子生物学が考古学の隣接分野になっているように専門家の研究範囲は拡大しているのだ。2025/02/27
月をみるもの
17
この数年、あちこちの古墳みてまわったり古代史の本を読んだりしてたのだが、この本を読んではじめて当時の列島の全体像というものが浮かんできた。文字に書かれた歴史のみを相手にする普通の(?)史学には決して到達しえない境地がここにある。では考古学の扱う「モノ」は文献と違って嘘をつかないか、、と言えば、決してそんなことはない。その限界を示す最もよく知られた実例が、この講談社「日本の歴史」シリーズの第1巻「縄文の生活誌」であるという皮肉。ある意味、文字以前の歴史を扱う1〜2巻は最強コンビであると言えるだろう。2019/02/16
coolflat
15
稲作が伝来する縄文時代晩期後半から弥生時代全期間を経て、「倭の五王」の出現前史となる古墳時代前期までを扱う。実年代ではおよそ前6世紀末から4世紀末までとなる。筆者によると、卑弥呼は「邪馬台国」の女王ではないという。では卑弥呼は何者かというと、卑弥呼は「倭国」の女王だと。曰く、「邪馬台国」とは、「倭国」の都があり、かつその女王である卑弥呼の居所であると。また筆者は日本国家成立期を、従来定説の694年藤原京遷都(天武・持統期)ではなく、弥生時代の卑弥呼女王期と捉えており、その根拠は纏向(まきむく)遺跡による。2020/02/07