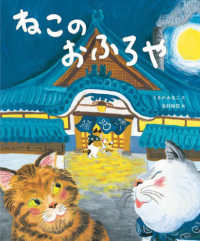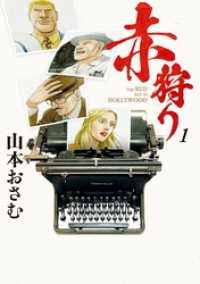出版社内容情報
単行本未収録インタヴュー集第一弾。イェール大学での講義を終えてからNAMでの活動を始める21世紀初頭までの発言と軌跡を辿る。単行本未収録インタヴュー集第一弾。
イェール大学での講義を終えてからNAMでの活動を始める21世紀初頭までの発言と軌跡を辿る。
※本書収録の13篇のうち「不可知の“階級”と『ブリュメール十八日』」は、情況出版編集部編『マルクスを読む』(1999年11月、情況出版)を底本とし、それ以外は初出紙誌を底本としました。
柄谷 行人[カラタニ コウジン]
著・文・その他
内容説明
初のアメリカ滞在後の一九七七年から、NAMの渦中にあった二〇〇一年まで、単行本未収録インタヴューを中心に十三篇集成。『日本近代文学の起源』『隠喩としての建築』『探究』『“戦前”の思考』『倫理21』と繋がる、強靱な思考の展開を、自らやさしく語りかける。世界と拮抗し、常にラジカルである“柄谷思想”の最高の入門書。さらには、柄谷行人の「哲学的バイオグラフィー」ともいえる一書。
目次
思想の世界性へ
“英語ができない”はありえない
孤立と連帯の新しいパラダイム(聞き手・島弘之)
不可知の“階級”と『ブリュメール十八日』
「戦前」の思考を巡って
文学・戦後五十年いかに対処するか(聞き手・石原千秋)
中上健次の魅力と実像
単独者とインターナショナリズム
資本と国家を超えて(聞き手・王寺賢太)
岩だらけの景色のなかで
「芸術」の外で、なお
文学と運動
飛躍と転回
著者等紹介
柄谷行人[カラタニコウジン]
1941・8・6~。批評家。兵庫県生まれ。1965年、東京大学経済学部卒業。67年、同大学大学院英文学修士課程修了。法政大学教授、近畿大学教授、コロンビア大学客員教授などを歴任。また批評誌「季刊思潮」「批評空間」を創刊。主な著書に『マルクスその可能性の中心』(亀井勝一郎賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。