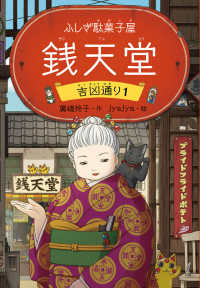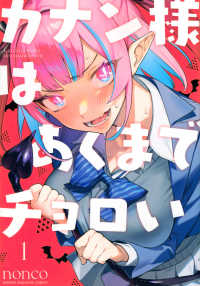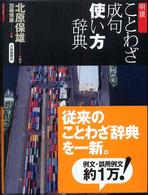出版社内容情報
阿川弘之の流麗かつ芳醇な訳で贈る、ポール・セルーのユーラシア一周汽車の旅。出会いと別れ。。各国各様の人生を乗せて・・・・・。
阿川弘之の流麗かつ芳醇な訳で贈る、ポール・セルーのユーラシア一周汽車の旅。出会いと別れ。。各国各様の人生を乗せて・・・・・。
内容説明
汽車の旅には人生がある。時には皮肉に、時には優しく、出会いがあり別れがある。汽車の旅には、試練がある。長い長い旅の途中、楽しみが苦痛に変わることもある。しかしそれを超えたとき、汽車の魅力は数倍の喜びとなる。各国の様々な人生を乗せて、ひたすらユーラシア大陸をセルーが、阿川が走る、世紀のドキュメント鉄道大旅行。
目次
マンダレー急行
各駅停車メイミョー行
「ラシオ・メイル」号
ノンカイ発夜行急行
国際急行列車バタワース行
クアラ・ルンプール行「ゴールデン・アロー」号
シンガポール行夜行急行「ノース・スター」号
サイゴン発ビエン・ホア行
ユエ発ダナン行旅客列車
青森行特急「はつかり」
札幌行特急「おおぞら」
京都へ―超特急「ひかり」
「こだま」号大阪行
シベリア横断急行(1 ソ連船「ハバロフスク」号;2 「東方」号;3 「ロシア」号))
著者等紹介
セルー,ポール[セルー,ポール][Theroux,Paul]
1941年、アメリカ・マサチューセッツ州生まれ。67年『ワルド』でデビュー。75年、アジアの旅を『鉄道大バザール』にまとめ、英米で大評判に
阿川弘之[アガワヒロユキ]
1920・12・24~。小説家。広島県生まれ。東京帝国大学卒業。卒業後、海軍入隊。終戦後、志賀直哉門下となる。1953年『春の城』で読売文学賞受賞。66年『山本五十六』で新潮社文学賞。94年『志賀直哉(上・下)』で野間文芸賞受賞。99年11月、文化勲章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
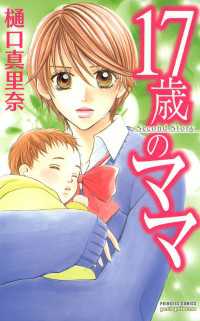
- 電子書籍
- 17歳のママ Second Story…