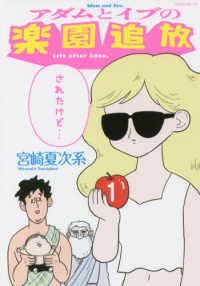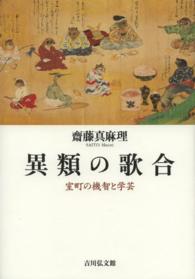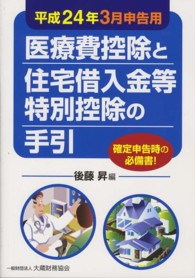内容説明
複雑な家庭環境の中での父と母の姿を印象的に綴った「石蹴り」、その父の老齢になっての入水自殺の顛末を追った「耳のなかの風の声」、花柳界に生きる女性とのはかない交流を辿る「なぎの葉考」「熱海糸川柳橋」など、名作九篇を収録。戦前、戦中、戦後と、時代に流されることなく、反骨精神をもって、市井の人生、暗い翳りをもつ女たちを描き続けてきた著者の「私小説」の精華を集成。
著者等紹介
野口冨士男[ノグチフジオ]
1911.7.4~1993.11.22。小説家。東京生まれ。慶応大学予科中退後、1933年、文化学院卒業。紀伊國屋出版部に入社、「行動」の編集に携わり、徳田秋声の「あらくれ会」にかかわる。40年、最初の著書『風の系譜』を刊行し、船山馨、田宮虎彦らと「青年芸術派」を結成、時流への抵抗を意図する。44年、横須賀海兵団に応召。45年、ひどい栄養失調で復員。この体験がのちに『海軍日記』となる。65年、15年かけた『徳田秋声伝』刊行。翌年、毎日芸術賞受賞。以後の活躍はめざましい。84年から88年まで日本文芸家協会理事長を務める。主な著書に『わが荷風』(読売文学賞)、『かくてありけり』(読売文学賞)、『なぎの葉考』(川端康成文学賞)、『感触的昭和文壇史』(菊池寛賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hasegawa noboru
13
「なぎの葉考」が一九八〇年の川端康成賞を受賞した時の吉行淳之介の選評の言葉が「ロマンがありいまやメルヘンでもある」(勝又浩・解説)だったそうな。いかにもな、さすがの言いよう。娼婦と過ごした一夜の交流の記憶。四十年の遠いむかし、戦前の昭和の頃を、芽の出ぬ私小説作家として生きていた「私」の暗い青春の一齣をふり返る。買った女とのやり取りがどうのと、現代のフェミニズムの観点に立てば、男ばかりのいい気な贅言と言えなくもないが、最底辺で生きた薄幸な女性たちがいてそういう親身な言葉もいっただろう、と思わせる小説の力。2021/12/03
fseigojp
9
中上健次がらみで読んでみました うーん2015/07/29
ヒ
7
ある程度色々の事に見切りをつけてものを書いている人の文章はやっぱり自分には読みやすいというか自分とかけはなれた感性を持った人の文章だとしてもおもしろく読むことができるなということを再確認した 藤枝静男の、身辺の事を書いた諸作をふまえているからこそ空気頭をおもしろく読めるのというのと同じ理由で、最後ふたつの短編「少女」と「横顔」が良かった それまでの家族や商売女にかんする作品がなかったらはたして同じような気持ちで読めたかどうかはわからない2019/08/24
あまたあるほし
4
美しすぎます。2010/07/13
ソングライン
3
なぎの葉考では、老年期に達した主人公が若き日に一度訪れた新宮にあった遊郭を訪ねる旅が描かれます。遠い過去となった思い出の場所を訪ね、その時であった娼婦を偲ぶ。今ならば共感できる短編です。少女は、誘拐犯と誘拐された少女のこころの交流を描いた作品です。不謹慎かもしれませんが、最後の少女の言葉が胸を打ちます。2016/06/22