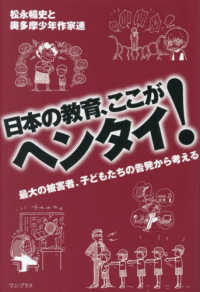出版社内容情報
長谷川 櫂[ハセガワ カイ]
著・文・その他
内容説明
「五・七・五」「切れ」「季語」―「約束」の理由を知れば自在に詠める。「朝日俳壇」、読売新聞「四季」等で人気の俳人による明快な俳句入門書。
目次
第1章 俳句の音楽
第2章 一物仕立てと取り合わせ
第3章 切れと切字
第4章 一物仕立てと取り合わせの見分け方
第5章 一物仕立てと取り合わせの詠み方
第6章 季語と季題
第7章 無季と季重なり
第8章 循環する時間
第9章 日本語の構造
著者等紹介
長谷川櫂[ハセガワカイ]
1954年、熊本県生まれ。俳人。俳句結社「古志」主宰、朝日俳壇選者、「季語と歳時記の会」代表。東京大学法学部卒業後、読売新聞記者を経て、俳句に専念。『俳句の宇宙』でサントリー学芸賞(1990年)、句集『虚空』で読売文学賞(2003年)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
13
こだわりの俳句道場という感じで初心者向きではない。芭蕉の例題が多く、芭蕉時代の俳句の考えを元にしている。それは近代俳句の写生というより音楽という感じ。最初に「切れ」の講釈も言葉の省略ではなく、間だという。カメラの切り替えのように考えていたが、間による場面変化なのだ。能のような。そのリズムが散文ではなく、韻文なのだ。俳諧が連歌から来ているのは、そうした場の音楽だった。その切れがあって、一物仕立てと二物衝動が出てくる。2021/06/22
松風
11
(一物仕立て、取り合わせに派生する)句切れについて特化して詳しい。が、これだけでは「入門」できないなぁ…。2014/07/16
y_nagaura
10
大和言葉は二音ないしは三音の単語を基礎とした言葉、一物仕立てと取り合わせの読み取り方、季語と季題の違いなど、俳句を読む(または詠む)うえで欠かせない見方が満載。芭蕉の句の魅力を中心に解説してくれるのも嬉しいポイント。 螺旋状の循環する時間認識に根ざす文芸観。太陽太陰暦と噛み合わない太陽暦と、歳時記のずれ。古来からの季節観を失いつつある現代日本。 言文一致運動により、話し言葉の暴走を食い止められなくなった。受容・選択・変容。無名という原則。一度きりということ。 俳句には、日本の美意識が凝縮されている。2018/10/27
てくてく
4
著者の俳句哲学みたいなものが綴られている。知っている俳句でも解釈が全く違うのだ(自分の解釈だと名句にはならない)ということや、類想が多くなってしまいがちな俳句という短い詩でどこまでオリジナリティを追求するのかという点が面白かった。2020/02/18
かがみ
3
俳句の「お約束」であるところの「定型」「切れ」「季語」を詳説する一冊。五・七・五からなる「定型」は二音と三音を基本とした大和言葉のリズムに由来し「切れ」は俳句に「間」をもたらし「季語」は俳句を宇宙のめぐりに組み入れるものである。そして季語と切れは車の両輪であり、季語は切れによって香り立ち、切れは季語を切る時にもっとも切れ味が良い。切れの生み出す「間」はノエマ的な無音ではなく、鑑賞者のノエシス的な作用としての「詩情」を生み出すメタノエシス的な「あいだ」として作用する。俳句は究極の「あいだ」の文学である。2024/08/29
-

- 電子書籍
- メガミマガジン2025年11月号
-
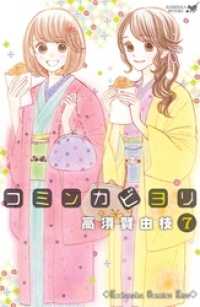
- 電子書籍
- コミンカビヨリ(7)