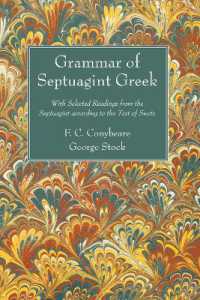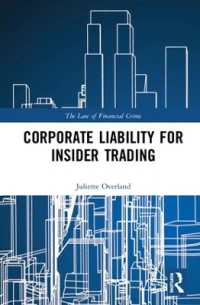出版社内容情報
「おもろい奴も、笑える話もあるで」
部落差別はまだまだ厳しいという悲観論があり、一方で楽観論もある。その「間」はどうなっているのだろう。普段は気にしないが、ある場面で差別にぶつかる。そんな人々の日常を書きたいと思った――。丹念な取材を通して語る結婚、ムラの暮らし、教育。しなやかな視線で「差別と被差別の現在」に迫るルポ。
角岡 伸彦[カドオカ ノブヒコ]
著・文・その他
野村 進[ノムラ ススム]
解説
内容説明
部落差別はまだまだ厳しいという悲観論があり、一方で楽観論もある。その「間」はどうなっているのだろう。普段は気にしないが、ある場面で差別にぶつかる。そんな人々の日常を書きたいと思った―。丹念な取材を通して語る結婚、ムラの暮らし、教育。しなやかな視線で「差別と被差別の現在」に迫るルポ。
目次
第1章 家族
第2章 選択
第3章 ムラ
第4章 食肉工場
第5章 伝える
著者等紹介
角岡伸彦[カドオカノブヒコ]
1963年、兵庫県加古川市生まれ。被差別部落に生まれ育つ。関西学院大学社会学部卒業。神戸新聞記者などを経て、フリーのノンフィクションライターに。現在は大阪市に在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
丸々ころりん
22
非差別部落 中学生の時でサラッと習った印象 食肉産業が盛んな地域に存在していることが多い 経済的に困窮し謂れの無い差別を受ける。 国が差別をなくす為 村の環境設備を進めれば逆差別と言われ… 人は誰かを下に見ることで自分の幸福度を計っているともある。 差別が残るという高齢者 差別はないと言う若者 それは高齢者は学校に行って勉強が出来っても,部落民という一括りで押さえつけられる。若者新しい学校で学び外の世界を見て部落を出ていけるという差だと思います。2025/09/21
えこ
22
現在では差別は少なくなってるし、若い子では全く知らない子もいてる。このままほっとけばみんなが知らない世の中になりそうに思うんだけど、授業で習ったり部落解放運動をしたり、その地域の住宅を低家賃にしたりする必要ってあるのかな?部落外から食肉工場で働きにきてる読書家だというお兄さんの「部落差別は迷信。だって差別する根拠がないもん」という言葉に納得。2015/08/27
まりもんママン゚+.*ʚ♡ɞ*.+゚
19
著者の「ホルモン奉行」がとても面白かったのでその流れでこちらも読んでみました。ところが本書はかなり切実な問題で感想を書くのが難しいです。今まで生きてきてこの手の話はスルーしてきましたが当事者の方々は本当に苦悶苦闘しながらも環境を切り開く努力をされたり又は「足掻いても仕方ない。このままでいいや」と開き直って生活をしておられるのだと実感しました。いろんな意味でこういう差別は無くなればいいと思いました。勉強になりました。2012/10/13
ロボット刑事K
17
被差別部落や同和問題、知識として知ってはいても、実体験として感じたことはありません。私の住む横浜が同和問題と余程縁遠いのか、部落民が差別の対象になること自体が理解できません。って言うより、例えば本人に部落出身をカミングアウトされても、それがなんなん?ってカンジですな。しかし、この種の差別が現存するのも事実。関西に住む教師をしてる友人がかなり苦労してる話も聞いてますし。☆4つ。部落に対する差別は無くなっても「差別」自体がなくなることはないと思います。弱い者達が更に弱い者を叩くのが人の世なのだと思っています。2022/02/18
Ikuto Nagura
13
東京出身の私には、身の回りに実感としての被差別部落も解放闘争も存在しない。でもというか、だからというか、私の内にも、被差別部落に対して漠然とした恐ろしさやかわいそうという感情を無自覚に持ってないとはいえない。この理由を、本書の被差別部落出身者の等身大の姿から考えると、彼らが旧体制下の身分を意識せざるを得ないのに対し、私がそんなものを考える機会がないからだと思い至る。であれば、例えば中上健次が被差別者の言葉を天皇の言葉に対置して意識していたように、もう一方の特権階級が今も温存されていることに根がありそうだ。2016/05/31
-

- 洋書
- Pipeline