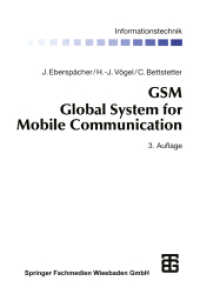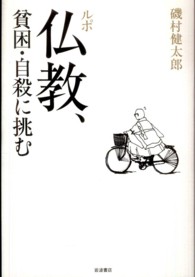内容説明
寺は気軽な場、葬式だけじゃもったいない。お寺カフェ、ライブ、ネット寺院にみんな集え。気鋭の僧侶が提言する「素晴らしいのにパッとしないニッポンのお坊さんへのエール」。
目次
第1章 お寺を変える実践―お寺カフェ/お寺の音楽会/バーチャル寺院
第2章 仏教コンテンツは21世紀の成長産業
第3章 私がお坊さんになった理由―「在家の僧侶」という生き方
第4章 日本仏教界の現状―飛び込んだ僧侶が見たもの
第5章 お寺の経営論
第6章 未来のお寺への提言―無限の可能性を引き出そう
第7章 世界の未来を切り開く仏教の技術
著者等紹介
松本圭介[マツモトケイスケ]
1979年、北海道に生まれる。法名・釈紹圭(しょうけい)。浄土真宗本願寺派僧侶、布教使。東京・神谷町光明寺所属。東京大学文学部哲学科卒業後、仏教界のトビラを叩く。超宗派仏教徒達のインターネット寺院「虚空山彼岸寺」を設立。光明寺仏教青年会代表として、お寺の音楽会「誰そ彼」や、光明寺の境内を活かした寺院内カフェ「神谷町オープンテラス」を運営(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おいしゃん
21
赤門を出て仏門に入った著者だが、今後仏教が生き残るためにどうすべきか、とても真剣に考えられてる印象を受けた。お寺カフェやお寺ライブなど斬新な取り組みが成功しているのも、このように根底の思想がしっかりしているからなのだろう。2021/10/30
かず
6
私は、仏教とは、「一切皆苦である人生を、如何に楽しく暮らすことが出来るようにするか」という実践哲学である、と捉えている。それに対し、現在のお寺のあり方は、葬式仏教と揶揄されるように、現実に生きる人々の苦悩に寄り添っていない、と考える。そして、それが、伝統仏教の凋落、新興宗教の興隆に繋がっている、と考える。本書は、東大哲学科を卒業した在家の男性が僧侶となり、その問題点を超克すべく奮闘された様々な事柄のリポートである。私も本書に同感である。仏教は死んだ人の為のものではない。今を生きる我々の為のものなのである。2015/01/11
Humbaba
4
時代と共に,宗教に求められることも変わってくる,そうであるのならば,僧侶もいつまでも昔ながらを繰り返していてはいけない.時代に合わせて変わっていくことが,今後の宗教に求められている.そうでなければ消えて行くしかないだろう.2011/08/08
月宮殿
3
仏教界に飛び込んだ著者の実体験と論点がリンクしていて示唆に富む。仏教の在り方に関心がある人にはオススメ。2011/01/05
ステラ
3
これからのお寺を担う20代〜40代の若手僧侶の方に読んで欲しい一冊。漠然とであっても現状に危機感を抱き、何かしないとなぁという思いがある方なら、大きな共感と刺激を受けると思う。2010/04/04