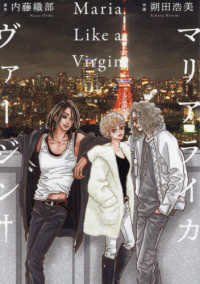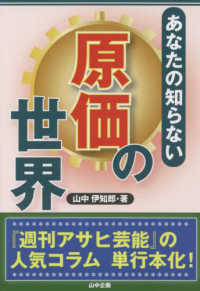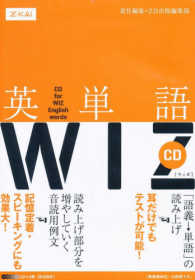出版社内容情報
物忘れ、注意力低下、人格豹変などにご用心! 「他人事ではない」恐怖の病の全貌と社会復帰のためのリハビリ法!物忘れ、注意力低下、人格豹変などにご用心!
「シャツに腕を通せなくなった」「昨日のことを覚えていない」
軽い転倒でも起こる! 「他人事ではない」恐怖の病の全貌と社会復帰のためのリハビリ法!
わが国の高次脳機能障害者は50万人をはるかに上回ると推定されます。いつ、自分の家族が交通事故や脳卒中で、高次脳機能障害になるかわかりません。けっして他人事ではないのです。私は、脳神経外科の救急現場に、8年間勤務しました。脳に大きな傷を負った人が昏睡状態で搬送され、外科治療を受け、やっとの思いで急性期治療を乗りきり、家族とともに安堵しながら病院をあとにしていきます。しかし、家に帰ってから問題は表面化します。脳が受けた傷によって家庭や社会に復帰する際に、大きな壁に直面するのです。しかし、脳の損傷による後遺症は、リハビリテーションによって大きな希望を見出せます。適切な刺激・環境によって、脳は健常者とは異なる部分が活性化し、数年をかけて再編されていくのです。
●「高次」とは何か
●20年前の事故が原因で精神科病院に
●脳は2階建て構造でできている
●悪い刺激が問題行動を引き起こす
●からだの回復とともにすべきこと
●家族がリハビリの隙間を埋める
●脳はどのように回復するのか
●心の障害へのリハビリテーション
●社会参加への第一歩を踏み出す
●高次脳機能障害者の心のいたみ
渡邉 修[ワタナベ シュウ]
著・文・その他
内容説明
軽い転倒でも起こる!「他人事ではない」恐怖の病の全貌と社会復帰のためのリハビリ法。
目次
第1章 高次脳機能障害とは何か(何が原因で発症するのか;「高次」とは何か ほか)
第2章 多様な症状を理解する(50歳の社長が脳梗塞になった;高次脳機能障害の10種の症状 ほか)
第3章 入院中に家族ができること(下校途中に車にはねられた;急性期に家族が知るべきこと ほか)
第4章 家族一丸となって臨むリハビリテーション(ダイビングの免許取得中に溺れた;社会復帰するまでの3つの時期 ほか)
第5章 地域で生活する(悠々自適な生活を送っていたのに;社会のなかで生きる技術を磨く ほか)
著者等紹介
渡邉修[ワタナベシュウ]
1960年、山梨県に生まれる。医学博士。日本リハビリテーション医学会専門医。浜松医科大学医学部卒業後、同大学脳神経外科にて臨床、研究に従事。1993年より、リハビリテーション科。東京慈恵会医科大学付属第三病院で数多くの高次脳機能障害の治療を経験。1995年より、スウェーデン・カロリンスカ病院臨床神経生理学部門に勤務。帰国後、神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション医学科医員。2004年、東京都調布市で高次脳機能障害者とその家族、ボランティアで運営するグループ「東京レインボー倶楽部」を立ち上げ、地域でのリハビリテーションの場をつくる。2005年、首都大学東京教授。患者とその家族のケアを最優先に治療している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤森かつき(Katsuki Fujimori)
アルカリオン
うさこ
ひろか
月のたまご