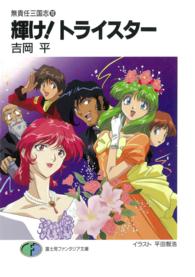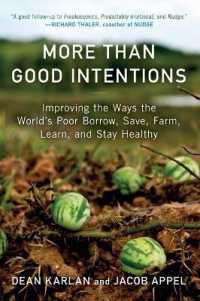出版社内容情報
発達障害研究の権威、杉山登志郎氏大絶賛!
「10年に1冊の画期的な人智科学の登場である」
視覚優位のアントニオ・ガウディと聴覚優位のルイス・キャロル。彼らの認知の偏りが偉大なる「サグラダ・ファミリア聖堂」や「不思議の国のアリス」を生み出した。発達障害の新たな可能性を探る衝撃の書。
様式によって異なる認知世界の地平へ
これまで多くの指摘がなされながら、正面から取り上げられることがなかった認知様式による体験世界の差異。それは人との関係も、学習も、仕事も、つまりはすべての活動を巻き込んだ構造的相違に展開する。視覚優位の世界、聴覚優位の世界、パースレスによる失認、そして局所優位性など……。読者は、認知様式の特徴を踏まえることで、多くの問題が容易に解決し、新たな教育の可能性が生まれることに、まさに目から鱗が落ちる体験をするであろう。10年に1冊の画期的な人智科学の登場である。――杉山登志郎
岡 南[オカ ミナミ]
著・文・その他
内容説明
視覚優位のアントニオ・ガウディと聴覚優位のルイス・キャロル。彼らの認知の偏りが偉大なる「サグラダ・ファミリア聖堂」や「不思議の国のアリス」を生み出した。発達障害の新たな可能性を探る衝撃の書。
目次
第1章 あなたは視覚優位か、聴覚優位か(「認知」とは何か;二つのタイプの優位性―「視覚優位」と「聴覚優位」;他にもある認知特徴による分類 ほか)
第2章 アントニオ・ガウディ「四次元の世界」(神の建築家ガウディ;生まれながらの資質;ガウディ自身が語る認知の特徴とは ほか)
第3章 ルイス・キャロルが生きた「不思議の国」(子どものような心を持つキャロル;生まれながらの資質;一方的な努力と困った行動 ほか)
著者等紹介
岡南[オカミナミ]
室内設計家。大同大学工学部建築学科非常勤講師。神奈川県生まれ。桑沢デザイン研究所・住宅インテリア研究科卒業。女性で初めて日本建築学会賞を受賞した林雅子氏などに学ぶ。第16回リフォームコンクール総合部門で、三次元空間での人の動きを想定した総合的なデザイン力への評価で優秀賞を受賞。会社社屋・美術館など主に公共建築物の内装設計および色彩計画を行っている。また、自身の映像思考から視覚認知の研究を、色彩や空間認知・神経学・発達障害などからの考察をも交え探求し、チャールズ・ダーウィンやルイス・キャロルなどをはじめ、才能と認知の偏りの関係を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ぷに
かお
まかほ
やすのり
A