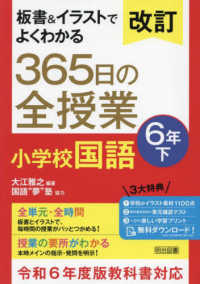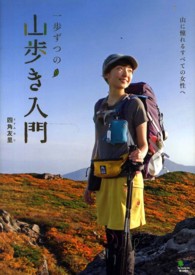出版社内容情報
なぜ、突然できるようになるのか? どうすれば、不調を味方につけられるか? 「からだメタ認知」で解き明かす身体知!自転車や車の運転から水泳、ゴルフ、仕事のやり方まで、「身体がおぼえる」、「こつをつかむ」、あるいは「スランプに陥る」のは、誰もが経験したことではないでしょうか。
本書は、そうした「身体に根ざした知」=「身体知」と、「身体知を学ぶ」とは一体どういうことなのかを、イチロー選手なども例にとりつつ、認知科学という立場から解明し、更に「身体知の研究はどうあるべきか」について明快に論じます。
こつをつかむにも、スランプを脱するにも、「ことば」が重要であるらしいことがわかってきました。
〈からだメタ認知〉という概念をキーワードに、身体とことばの共創をめぐる最先端の研究を、わかりやすく紹介します。
目次
第一章 身体知の魅力
1 説明できるヒット
2 居心地を判別するからだ
3 感性は身体知
4 まち歩きを楽しむ身体知
5 身体知とはなにか?
第二章 身体知をどう捉えるか
1 身体知 vs. 科学
2 スポーツ科学とその限界
3 現象の「生成」を探る身体知研究
4 ことばは身体知の学びの敵なのか?
第三章 情報処理モデルから認知カップリングへ
1 情報処理という思想
2 情報処理モデルの限界
3 認知カップリングと身体知
第四章 身体知研究のあり方
1 暗黙知と身体知
2 ことばのシステムと身体のシステム
3 個人固有性
4 コト研究と身体知
第五章 身体とことばの共創を生む学びのメソッド
1 からだメタ認知
2 何をことばで表現するか
3 創作オノマトペで体感をことばにする
4 身体とことばの共創
第六章 スランプを乗り越え、こつを体得する
1 ボウリングの身体知
2 スランプはなぜ必要か
3 学びの既存理論 vs. からだメタ認知
第七章 身体知研究の最前線
1 一人称研究――一人称視点の記述に基づく仮説生成
2 構成的研究――学ばせながら学びの様を観察・探究する
3 生活研究――研究と生活を切り離さない
4 ことばの分析――プロトコル・アナリシスの手法
第八章 身体知研究のこれから
1 体感を探究する時代へ
2 「足触り」の研究
3 体感データに基づく身体知研究のシナリオ
4 まだまだ神秘なる身体知
諏訪 正樹[スワ マサキ]
著・文・その他
内容説明
内角高めの球を打つ、料理の火加減を調節する、説得力あるプレゼンをする…スランプではことばが増え、こつをつかむと体感で御す。「からだ」の学びに、なぜ「ことば」が必要なのか?身体知の解明に挑む、認知科学の最前線!
目次
第1章 身体知の魅力
第2章 身体知をどう捉えるか
第3章 情報処理モデルから認知カップリングへ
第4章 身体知研究のあり方
第5章 身体とことばの共創を生む学びのメソッド
第6章 スランプを乗り越え、こつを体得する
第7章 身体知研究の最前線
第8章 身体知研究のこれから
著者等紹介
諏訪正樹[スワマサキ]
1962年大阪生まれ。慶應義塾大学環境情報学部教授。工学博士。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。(株)日立製作所基礎研究所、シドニー大学建築デザイン学科主任研究員、中京大学情報理工学部教授などを経て現職。身体知の学び、コミュニケーションのデザインを専門領域とする。自ら野球選手として打撃スキルを磨かんとする実践(フィールドに出た構成的研究)から、学び理論「からだメタ認知」を提唱し、身体知を探究してきた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
りー
羊山羊
かっさん
田中AD
-

- 和書
- 建築家の椅子111脚