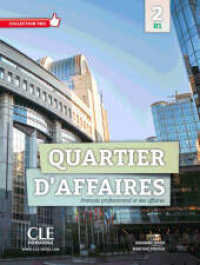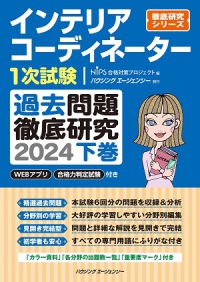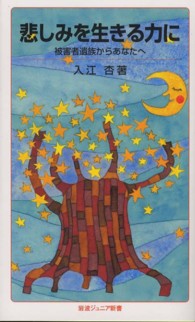出版社内容情報
中沢新一氏推薦!
この輝くような若い日本の知性は、死せるレーニンを灰の中から立ち上がらせようと試みたのだった。ゾンビではない。失敗に帰した自らの企ての廃墟に佇みながら、ここに創造された21世紀のレーニンは、永遠に続く闘争への道を、ふたたび歩みだそうとしているかのように見える。素っ気ない手つきで差し出されたこの本が、世界へのまたとない贈り物であったことにみんなが気づくまで、そんなに時間はかかるまい。
資本主義の「外部」とは? 革命観のコペルニクス的転回とは? 『国家と革命』、『何をなすべきか?』という2つのテクストから立ち現れる、「リアルなもの」の探求者の思考の軌跡。資本主義の純粋化が進む現在、レーニンという思想史上の事件を捉え直す。
第1部 躍動する<力>の思想をめぐって
第1章 いま、レーニンをどう読むか?
第2章 一元論的<力>の存在論
第2部 『何をなすべきか?』をめぐって
第3章 <外部>の思想――レーニンとフロイト(1)
第4章 革命の欲動、欲動の革命――レーニンとフロイト(2)
第3部 『国家と革命』をめぐって
第5章 <力>の経路――『国家と革命』の一元論的読解(1)
第6章 <力>の生成――『国家と革命』の一元論的読解(2)
第7章 <力>の運命――『国家と革命』の一元論的読解(3)
白井 聡[シライ サトシ]
著・文・その他
内容説明
資本主義の「外部」とは?革命観のコペルニクス的転回とは?『国家と革命』、『何をなすべきか?』という二つのテクストから立ち現れる、「リアルなもの」の探求者の思考の軌跡。資本主義の純粋化が進む現在、レーニンという思想史上の事件を捉え直す。
目次
第1部 躍動する“力”の思想をめぐって(いま、レーニンをどう読むか?;一元論的“力”の存在論)
第2部 『何をなすべきか?』をめぐって(“外部”の思想―レーニンとフロイト(1)
革命の欲動、欲動の革命―レーニンとフロイト(2))
第3部 『国家と革命』をめぐって(“力”の経路―『国家と革命』の一元論的読解(1)
“力”の生成―『国家と革命』の一元論的読解(2)
“力”の運命―『国家と革命』の一元論的読解(3))
著者等紹介
白井聡[シライサトシ]
1977年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位修得退学。現在、日本学術振興会特別研究員。多摩美術大学、神奈川大学非常勤講師。専攻は、政治学・政治思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なっぢ@断捨離実行中
さえきかずひこ
amanon
嘉月堂
Mealla0v0
-

- 和書
- チーム担任制