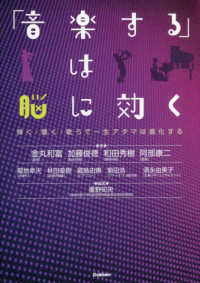内容説明
天狗・魔王が跳梁し、神仏の声響く“魔仏一如”の世界=中世。膨大な偽書はなぜ書かれたのか。新仏教を生みだした精神風土はなにか。混沌と豊穣の世界に分け入り、多彩な思想を生みだす力の根源に迫る。
目次
序章 偽書の精神史へ
第1章 新仏教と本覚思想のあいだ
第2章 偽書の時代としての中世
第3章 偽書はいかにして作られるか
第4章 中世的コスモロジーと偽書
第5章 鎌倉新仏教の誕生
第6章 偽書を超えて
著者等紹介
佐藤弘夫[サトウヒロオ]
1953年生まれ。東北大学文学部史学科卒業。同大学大学院文学研究科博士前期課程修了。現在、東北大学大学院文学研究科教授。専門は日本中世思想史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
58
【偽書は、日本中世や古今東西を問わずどこにでもみられる普遍的な現象である】“偽書”をキーワードに、さまざまな思想的な営みの根源にある中世人の思考方法の特色を明らかにした書。巻末に、引用参照文献一覧と索引。2002年刊。<仏教学では、中国や日本で後世に作られた経典を「偽経」と呼んでいる。だが仏教の根本聖典である経典そのものが、厳密に言えば釋迦の名を借りた偽経にほかならない。宗教者の思想に論理を超えた主観性が存することも決して珍しいことではない。それはある意味では信仰の信仰たるゆえんであった>と。確かに……⇒2025/02/05
たばかる
16
2002著。仏教説話に出てくる怪異や神秘体験、或いは実現してから書かれた予言書などを偽書とくくってその成立をもたらした時代背景を分析する。テーマの時点では面白い。権現、本地垂迹に焦点が当てられ、悪鬼や昔の偉人の姿を借りた神仏という書かれ方の中に当時の信仰の様子を推察できる。例では、万人の救済をし見守る崇高な存在と一人の神頼みな落伍者に肩入れするものとの間の差が挙げられている。後半には偽書を生み出すような権威ばりな新仏教の話とかそれに反対する日蓮の話になるが些かページを割きすぎな印象を受けた。2019/07/07
ニゴディー
4
なかなか興味深い。 「これは偽書だからダメ」「これは真書だからOK」みたいな否定的な内容ではなく、なぜ偽書が生まれたのか、どういう位置づけなのかといった背景にも目を向けられている。 鎌倉仏教に関連する話題が多めなので、単純に偽書に興味があるだけだとちょっとおもしろくないかも。 もっとエンタメ寄りの文章だと良かったかな。2024/12/17
がんぞ
4
鎌倉時代、偽史が歴史的証明のように受け取られたのに対し、江戸時代には偽史がほとんど無くなったという論点は良いが。題名に即した論文に依存するだけで、オリジンリティーがない/著者は、創価学会の理論武装の重鎮らしいが、末法御本仏日蓮を親鸞と比較し「現実と真剣に取り組んだ」などと抽象的表現で比較するのは崔尊入卑に当たる。「世界的偉人と汝の師匠は原発事故を予測していたか、防ぐため何をしたか」聞いてみたい。このところ姿を見せないので青壮年部のマインドコントロールは解けかけてきている。ストーリーを信じる振り,心酔わす酒2011/11/27
非実在の構想
3
中世、偽書を作成して憚らなかったのは自分の思想は自分と一体である仏に由るものであるという信念があったためであり、本覚思想に基づいていた。2019/11/09