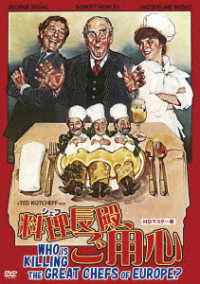内容説明
大人の目には映らない、心のありのままが見えてくる。自分とは、生とは、死とは、心の悩みや痛みとは…誰もが直面する人生の問題が、思いがけない形で映しだされる。心理療法家の心を深く捉えた12の物語。
目次
序章 なぜ子どもの本か
第1章 大人と子どもの間―ケストナー『飛ぶ教室』
第2章 孤独を生きるとき―ピアス『まぼろしの小さい犬』
第3章 幻想の世界、現実の世界―ロビンソン『思い出のマーニー』
第4章 ときの流れ、いのちの流れ―今江祥智『ぼんぼん』『兄貴』『おれたちのおふくろ』
第5章 たましいの国に住む―ヘルトリング『ヒルベルという子がいた』
第6章 子どもの輝き―リンドグレーン『長くつ下のピッピ』『ピッピ船にのる』『ピッピ南の島へ』
第7章 「もう一つの世界」を知ったとき―ゴッデン『ねずみ女房』
第8章 「もう一人の私」がいる―ボーゲル『ふたりのひみつ』
第9章 非日常を生きる―長新太『つみつみニュー』他
第10章 愛を問う―スナイダー『首のないキューピッド』
第11章 「第三の道」ができるまで―ハンター『砦』
第12章 異性の世界―佐野洋子『わたしが妹だったとき』
1 ~ 1件/全1件
- 評価
電子化待ちタイトル本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
昭和っ子
26
何回読んでもドキッとする箇所が必ずある。「子供の頃の事をよく覚えている女の人は、一番のなかよしという問題をめぐって、死にたくなったり、誰かが死んじゃえばいいのにと思ったりした事を思い出される事だろう。そんな事を一度も経験した事のない女性は、不幸な人と言わねばならない」(p243)こんな事を経験する方が不幸だとばかり思っていたのに!「たましい」の問題は一筋縄ではいかないと、何度も言及されている。子供の交友関係に大人の常識で割り込んだりせず、とりあえずはじっと見ていよう、と、ここで思ったのを思い出した。2015/04/27
佐島楓
25
児童文学の分析書。いつも思うこと。河合先生の御本は平易な日本語で書かれているのに、内容が理解できないことがままある。私の中で受け入れきれない「何か」があるということなのだろうか。「たましい」の世界に近いのが子ども。なぜ一部の大人は子どもを軽んじたり侮ったりできるのだろう。私は少なくともできない。2014/02/25
musis
19
本当に興味深く、面白かった。何気なく読んでいた児童文学がこんなにも広く深い意味を持っている。思い出のマーニ―の解説が面白かったので今回手にとったが、読んでよかった。学生時代、臨床心理士の先生がたが語る心理療法のケースにおいていつもクライエントのことが愛しい気持ちになった。主訴やその状況に関係なく、心理士はケースにおける事実のみ語っている場合でもそうだった。それは、心理士がクライエントの言動について適切に観察し的確な動詞、形容詞、副詞など使い説明することも一因でないかと今回思った。…また勉強し直してみたい。2017/03/28
アオイトリ
18
再読)今年の総括に原点回帰。大好きな河合隼雄先生のお話を聞きたくなった。自然科学の体系や社会生活をぐらつかせてしまう「たましい」(あるいは心身を越える第三領域)の話は時々取り出しては、大切に味わい、軌道修正できるくらいがちょうどいい。物語の世界観を全力で共有しながら、溺れないところで佇んでいる慈父のような河合先生が懐かしい。この年越しは児童書を読みつつ…2021/12/26
daidai
11
受講中の講座の関連本として読む。 河合隼雄先生が児童文学を心理学者の立場から解説していく。単なる解説本ではない。 児童文学はストーリーだけおっていけば、大人の本と比べて単調でつまらないのかもしれないが、内容は単に読者を楽しませるというものではなく、「生」を扱っているということがヒシヒシと伝わってくる。 ファンタジーと空想小説は違う。単に想像して書いたものでは子どもの魂は揺さぶることができない。ファンタジー作家がそこまで自分の命をかけて書いているとは驚きだ。2016/11/09