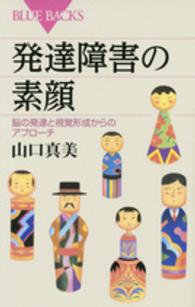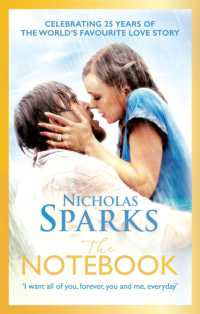出版社内容情報
被災地で、老人ホームで、病院で、猫の持つ「癒やし」の力を探る。かわいい猫の写真がいっぱい「猫には、苦しむ人をよみがえらせる力がある。猫は偉大だ!」――ノンフィクションライター野村進氏推薦!
セラピーキャットの「ヒメ」は、白猫のメス。アニマルセラピーを実践する飼い主に、セラピーキャットとして育てられてきた。
ヒメを撫でると、病に苦しむ人が笑顔を見せる、名前を呼ぶ。ヒメも自分から患者の膝に乗っているようなのだ――。
2015年、猫の飼育数が犬を逆転しました。いま日本で飼われている猫の数は、約987万4千匹。空前の猫ブームが訪れています。犬と違い、飼い主の言うことなんて絶対聞かないのに、猫を抱くとなぜこんなに癒やされるのでしょうか。
長年アニマルセラピーを取材してきた著者が猫の癒やしの謎に迫ります。
原発事故後のシェルターで飼い主を待ちつづける猫、飼い主と一緒に老人ホームで暮らす猫、認知症、統合失調症、知的障害などを抱えた人に寄り添うセラピーキャット。猫の「心」と出会う旅が始まります。
第37回講談社ノンフィクション賞、第58回日本ジャーナリスト会議賞(JCJ賞)受賞後第一作。
かわいい猫の写真がいっぱいです。
◇第1章 原発事故後の猫たち
原発事故後に警戒区域に取り残され、シェルターに保護された猫たちは――
◇第2章 セラピーアニマルとしての猫
犬のように訓練することのできない猫には、どのようなセラピーが可能か?
◇第3章 認知症の人たちのセラピー
小さいころからセラピーキャットとして育てられてきた白猫の「ヒメ」。寝たきりの人もいる介護療養病棟で、ヒメとの触れあいは認知症の人たちに何をもたらしたか?
◇第4章 障害のある人たちのセラピー
自閉症や知的障害、身体的障害などがある人たちの胸に、ヒメは飛び込んでいく。毛並みの向きと反対方向に撫でられたり、荒っぽく体をつかまれたりしても、ヒメは怒らない。障害をもつ人と健常者を、ヒメは判別しているようだ。
◇第5章 精神疾患の人たちのセラピー
精神疾患に対するキャットセラピーの有効性とは
◇第6章 猫はなぜ人を癒やせるのか
ヒメと人との心温まる交流
◇第7章 すべての猫はセラピストだ
死にゆく子どもに寄り添って
眞並 恭介[シンナミ キョウスケ]
著・文・その他
内容説明
セラピーキャットのヒメは、白猫のメス。アニマルセラピーを実践する飼い主に、セラピーキャットとして育てられてきた。ヒメを撫でると、病に苦しむ人が笑顔を見せる、名前を呼ぶ。ヒメも自分から患者の膝に乗っているようなのだ―。猫の「深い心」を探る、講談社ノンフィクション賞受賞第一作。
目次
第1章 原発事故後の猫たち
第2章 セラピーアニマルとしての猫
第3章 認知症の人たちのセラピー
第4章 障害のある人たちのセラピー
第5章 精神疾患の人たちのセラピー
第6章 猫はなぜ人を癒やせるのか
第7章 すべての猫はセラピストだ
著者等紹介
眞並恭介[シンナミキョウスケ]
ノンフィクション作家。1951年、大阪府茨木市生まれ。北海道大学文学部卒業。出版社、編集プロダクション勤務を経て、1992年にライブストーン株式会社を設立、代表取締役に。主に医学・医療分野の雑誌・書籍の編集・出版に従事。2002~2014年、毎日新聞大阪本社特約記者。『牛と土 福島、3.11その後。』(集英社)で第37回講談社ノンフィクション賞と第58回日本ジャーナリスト会議賞(JCJ賞)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みかん🍊
7a
Humbaba
patapon
gasparl