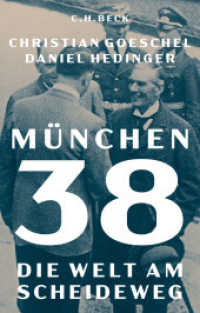出版社内容情報
おみやげは、世界無二の文化である。鉄道・軍隊・博覧会…近代の装置と土地の歴史とが生んだ奇妙で愛すべき存在を、本気で考察する!日本各地に無数に存在する「おみやげ」は、実は日本近代が生んだ独特の文化だった!
鉄道をはじめとした「近代の装置」が、土地の歴史や産物とむすびついて「名物」が生み出されていくさまを、膨大な史料を徹底的に読み込んで、鮮やかに描き出す! きびだんごはなぜ岡山名物なのか、安倍川餅は餅ではなく「求肥」、赤福は実は新しい伊勢名物だった、北海道になぜバナナ饅頭があるのか……こんなトリビアからはじまる本格歴史研究!
団子ひとつにも歴史ドラマがつまっている!
序章 おみやげの起源とおみやげ文化
日本の特異なおみやげ文化/神社仏閣とおみやげの起源/「名物」と「みやげ」
第1章 鉄道と近代おみやげの登場
鉄道の開通と名物の変容/安倍川餅と山葵漬/黍団子と吉備団子/八つ橋、メジャーになるまでの遠い道 ほか
第2章 近代伊勢参宮と赤福
明治天皇に届けられた赤福/近鉄電車と構内販売 ほか
第3章 博覧会と名物
博覧会と名物の創出/「外客誘致」とおみやげ改良 ほか
第4章 帝国日本の拡大と名物の展開
近世後期に生まれた宮島細工/創出の物語──もみじ饅頭と伊藤博文伝説/バナナと北海道/新領土台湾とおみやげ ほか
第5章 温泉観光とおみやげ
昭和から観光化が進展/温泉饅頭の誕生/坊っちゃんはどこで団子を食べたのか ほか
第6章 現代社会の変容とおみやげ
ドライブインの登場/おみやげ屋+レストラン=ドライブイン/高速な交通機関がもたらす変容/当初は不人気だった萩の月/イメージ戦略が当たった白い恋人/東京駅と羽田空港の発展に合わせて/バナナと「ばな奈」/「いやげ物」とペナント ほか
終章 近代の国民経験とおみやげ
鈴木 勇一郎[スズキ ユウイチロウ]
著・文・その他
内容説明
日本各地の駅を訪れると、饅頭や羊羹、弁当などの食品が、その土地の名物として売られている。私たちにとって当たり前のこの光景は、実は他の国ではほとんど見られない(ロンドンのターミナルで「ビッグベン当」のようなものは見あたらない)。この類い稀なる「おみやげ」という存在は、鉄道を筆頭とする「近代の装置」が、日本の歴史、文化と相互作用して生まれたものだった―。近代おみやげの誕生と発展のありさまを描き出す、本格的歴史研究。
目次
序章 おみやげの起源とおみやげ文化
第1章 鉄道と近代おみやげの登場
第2章 近代伊勢参宮と赤福
第3章 博覧会と名物
第4章 帝国日本の拡大と名物の展開
第5章 温泉観光とおみやげ
第6章 現代社会の変容とおみやげ
終章 近代の国民経験とおみやげ
著者等紹介
鈴木勇一郎[スズキユウイチロウ]
1972年、和歌山県生まれ。青山学院大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(歴史学)。専攻は日本近代史、近代都市史。現在、立教大学立教学院史資料センター学術調査員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
はちてん
雲をみるひと
Nobuko Hashimoto
ようはん
-

- 電子書籍
- 凡人でもエリートに勝てるマインド&習慣…
-
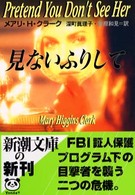
- 和書
- 見ないふりして 新潮文庫