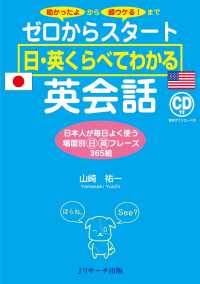出版社内容情報
麻薬、窃盗、暴行。問題を抱えた10代の少女たちが、介助犬を育てる経験をとおして再生していく姿を追った感動ノンフィクション!
麻薬、窃盗、暴行。問題を抱えた10代の少女たちが、介助犬を育てる経験をとおして再生していく姿を追った感動ノンフィクション!
内容説明
アメリカ・カリフォルニア州にある「シエラ・ユース・センター」。ここでは非行をした少女たちが、社会できちんと生活できるようになるための教育の一環として、介助犬を訓練する「ドッグ・プログラム」が行われています。障害をもつ人の日常生活を手助けする介助犬を育てる―。その経験をとおして、さまざまな問題や生きづらさを抱えた少女たちが、少しずつ変わっていきます。
目次
第1章 少女更生施設で介助犬を育てる
第2章 エイミーという少女
第3章 わたしはぜったい逃げない
第4章 再出発
第5章 成長する少女たち
第6章 介助犬の旅立ち
著者等紹介
大塚敦子[オオツカアツコ]
1960年和歌山市生まれ。上智大学文学部英文学科卒業。商社勤務を経てフォトジャーナリストとなる。エイズとともに生きた女性の記録で、98年度「準太陽賞」を受賞、『いのちの贈りもの―犬、猫、小鳥、そして夫へ』(岩波書店)にまとめる。写真絵本『さよなら エルマおばあさん』(小学館)で、2001年講談社出版文化賞絵本賞、小学館児童出版文化賞受賞。『平和の種をまく ボスニアの少女エミナ』(岩崎書店)が2008年青少年読書感想文全国コンクール小学校高学年の部の課題図書に選定(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。