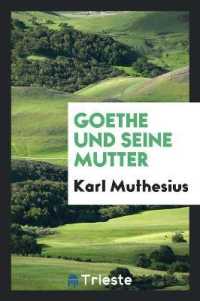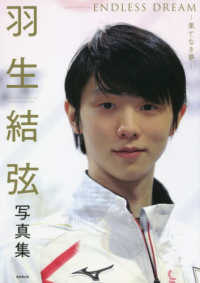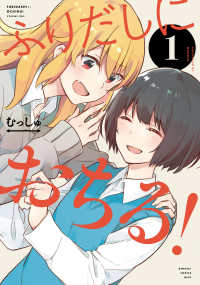- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > アニメ系
- > アニメ研究本、マンガ論
内容説明
全創刊誌を解析、初公開の秘話で「マンガが熱かった時代」が蘇る。
目次
第1章 月刊誌・赤本マンガ・貸本マンガ(一九四五年~一九五九年)
第2章 「サンデー」と「マガジン」(一九五九年~一九六五年)
第3章 「キング」「ジャンプ」「チャンピオン」(一九六三年~一九七五年)
第4章 劇画の「マガジン」、ラブコメの「サンデー」(一九六五年~一九八〇年)
第5章 成年誌と青年誌(一九五六年~一九八〇年)
著者等紹介
幸森軍也[コウモリイクヤ]
作家、株式会社ダイナミックプロダクション出版企画部部長。1961年兵庫県生まれ。関西大学商学部卒業。1989年株式会社ダイナミックプロダクションに入社。1992年『げんまん』(野性時代/角川書店)で作家デビュー。数多くのコミック著作権関連訴訟の陣頭に立つ。現在、専修大学文学部で日本文化研究の講座を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
マンガ道の本棚
-
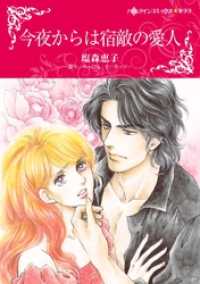
- 電子書籍
- 今夜からは宿敵の愛人【分冊】 10巻 …