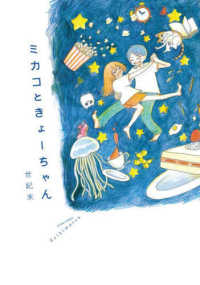内容説明
官能の矢に射られたわたしは修道女。熟年の女が第二の人生を送る修道院を訪れた作家。かしましい尼僧たちが噂するのは、弓道が引き起こした“駆け落ち”だった。時と国境を超えて女性の生と性が立ちのぼる、書き下ろし長篇小説。
著者等紹介
多和田葉子[タワダヨウコ]
作家。1960年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。ハンブルグ大学修士課程、チューリッヒ大学博士課程修了。1982年よりドイツに在住し、日本語とドイツ語で作品を手がける。1991年『かかとを失くして』で群像新人文学賞、1993年『犬婿入り』で芥川賞、1996年シャミッソー文学賞、2000年『ヒナギクのお茶の場合』で泉鏡花文学賞、2002年『球形時間』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、『容疑者の夜行列車』で谷崎潤一郎賞、伊藤整文学賞、2005年ゲーテ・メダル、2009年坪内逍瑶大賞など受賞多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
160
多和田さんの「聖女伝説」に引き続いての読書です。場所はドイツのとある修道院で、そこにいる人に日本語であだ名を付けていて読みやすく感じられました。修道院長がいない理由、二部でのその修道院長の話がゆったりとした感じで語られて私は前の本より楽しめました。オイゲン・へリゲルの弓についても若干触れられていて、このような解釈の仕方もあるのかとおもいました。2016/04/26
ヴェネツィア
117
今日的かつインターナショナルな小説だ。この作品がドイツの尼僧院を舞台にしているからというだけが理由ではない。この小説が英語で書かれていても、あるいはドイツ語で書かれていてもよかったと思うのだ。そこにどれほどの違いがあっただろう。そして、まさにその点にこそこの小説のこれまでにはない斬新さがある。もっとも、だからといって作品が日本語の固有性を失っているというのではない。素材の上からは「弓」に象徴される諸々が西欧的なものと対置されている。テーマもまた、「還るべき場所」をめぐってある種の普遍性の中に置かれていた。2013/08/01
どんぐり
90
日本人のわたし(作家)がドイツにある尼僧修道院で尼僧の生活を参与観察した「遠方からの客」と「翼のない矢」の小説2編。多和田さん特異の「弓道」と「キューピッド」の語呂合わせや、透明美さん、老桃さん、陰休さん、貴岸さんなど日本の名を付けた尼僧たちがいわくありげに登場する(ルビがないので、適当に読む)。「翼のない矢」は、尼僧院長が修道院まで追ってきた恋愛関係にある男に連れ去られる話。「遠方からの客」のほうは、尼僧院長が不在の修道院の女性たちの生活を描いている。→2023/08/12
りつこ
32
うあー、やっぱり好きだなぁ、多和田葉子!主人公と尼僧たちとの距離感が絶妙。え?そんなにいきなり核心に?と思わせたかと思うとさっと後ずさる。これからなにか起きるのか?とドキドキしてると、ささっと終わり、第二部へ。ええー?と思っていると第二部は一部で大いなる謎であった尼僧院長が語り手。今度は赤裸々に内面が語られ、うおーそういうことだったのか、とわかったようなわからなかったような。このふわふわ感が癖になるなぁ!面白かった~。2012/07/17
take0
29
第一部では尼僧院という信仰心で結び付いて共同生活を営む女性達の相関が、部外者である語り手の眼差しを通して語られる。アイロニーとユーモアがちりばめられ、軽妙さと鋭さを併せ持った筆致は多和田さんならではの比類のなさ。第二部では男性との恋愛で尼僧院を辞めたとされる元尼僧院長による半生と尼僧院を辞めた顛末が語られていて、第二部を読み終えガラリと変わった印象と共に、何とも言えない寄る辺なさを味わう。結局真相なんて誰にも分からないのかも知れない。どうしてそうなってしまったのか、当の本人にだって分かりはしないのかも。2019/02/21
-

- 和書
- 社会保障運動読本