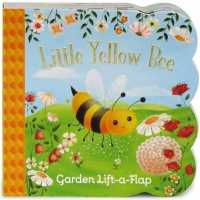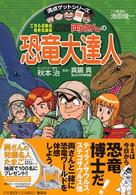- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
江戸で一番おいしい御飯を食べたのは誰?TVドラマ『JIN‐仁‐』の時代考証を担当する著者が、江戸の味がどのようにしてできたかを解明する。
目次
第1章 こうして決まった江戸好みの味
第2章 一番おいしい御飯を食べたのは誰
第3章 将軍の食事、庶民の食事
第4章 江戸が目指した地産地消
第5章 江戸前の魚と魚河岸の喧騒
第6章 下りものVS地廻りもの
第7章 屋台と茶屋
第8章 菓子と水菓子
第9章 四季の味覚
著者等紹介
山田順子[ヤマダジュンコ]
1953年広島県生まれ。専修大学文学部人文学科卒業。コピーライター、CMディレクターを経て、放送作家となる。1982年からNHK『クイズ面白ゼミナール』の歴史クイズの出題・構成を担当。以後、数多くのクイズ番組、歴史番組の時代考証と構成を手がけ、2009年にはTBSドラマ『JIN‐仁‐』の時代考証を担当。テレビ番組のほかにも、江戸東京博物館のインタラクティブ映像『世界の中の江戸東京』、ゲームソフト『バックトゥザ江戸』の出題と構成も担当した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
紅羽
11
興味津々な江戸時代のグルメ事情。普段見ている時代劇や時代モノを扱う作品に、こんな多くの矛盾がある事が分かり、面白かったです。江戸時代の始め頃は台所で腕を振るうのも、お店で調理するのも全て男性の仕事だったのは驚きです。当時の女性は調理の補助だけとは…。昔の主婦は楽々だったのかしら。すると女性の家事の負担が重くなるのは明治以降からなんですかね。他にも一番美味しい物を食べてそうな将軍の食卓が、そうでもなかったりと目から鱗な一冊でした。2015/09/08
るう
9
毎日何気なく食している日本食はほぼ江戸時代に確立されていたのに驚いた。醤油・味噌・味醂など基本的な調味料が作られ、東京湾からの新鮮な魚を工夫して食べられるようになったり、屋台や料理屋が繁盛してたり、各地の美味しいものが江戸に入ってきたりと、豊かな食生活が浮世絵や料理番付から分かる。江戸ではお米や砂糖もよく食していたし、見栄っ張りな江戸っ子は旬のものや高級食材もよく食べていたことに豊かな心を持っていたことを感じた。もっと「江戸」を知りたくなった。2015/05/06
ねこ太
5
当時の江戸、新興都市としての魅力があったんだろうな。男、しかも労働者が多いから塩気が好まれたし、お総菜やさんとか独り身でも暮らしやすそうだ。江戸初期は漁があまりさかんじゃなかったのには驚かされた。将軍、大奥の食事に興味ひかれた。2011/02/25
ちばっち
4
頭を捻り、隙間産業で色々な商売を産み出した江戸時代の人は凄いです。女の人が少なく、一人暮らしや単身赴任の男の人ばかりだったので棒手振りから買ったり、屋台で小腹を満たしたりとお手軽に食事をしているのに驚きました。権力のある将軍が一番美味しいものを食べているのかと思いきや、あんなに不味そうな食事をしていた事にビックリしました。そりゃ家定も家庭菜園するよなぁ…という感じです。江戸時代の食文化がイキイキと伝わってくる本です。2015/04/03
ひなぎく ゆうこ
3
★★★★☆2017/06/20