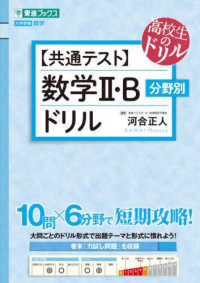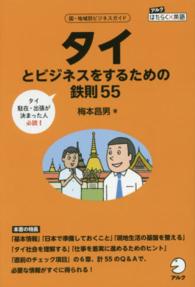出版社内容情報
京に負けない「都」をつくりたいと願った徳川の夢と都市計画を読む
浅草に三十三間堂、品川に大仏、上野に清水寺があった……
(1657年に焼け落ちた)天守閣は再建されなかったのである。幕府が困窮していたとか、太平の世にあって必要としなかったともいわれるが、筆者が思うに、これは図像学上不要だったからではなかろうか。戦国時代には高くそびえる天守閣が必要不可欠だった。しかし、これは城主が人民を見下ろすことを可能にすると同時に、人民が城主を下から見上げることも可能にしてしまった。しかし、古来東アジア全域で統治者は見られるということを嫌ったのである。これはヨーロッパとはまったく逆だった。(略)これに対して、徳川幕府は、自らの姿を隠したのである。
まえがき 江戸の再発見
第1章 日本橋、道の始まり
第2章 新しい京・江戸
第3章 江戸聖地巡礼
第4章 歌枕を求めて
第5章 吉原通いの図像学
タイモン・スクリーチ[タイモン スクリーチ]
著・文・その他
森下 正昭[モリシタ マサアキ]
翻訳
内容説明
浅草に三十三間堂、品川に大仏、上野に清水寺があった…京に負けない「都」をつくりたいと願った徳川の夢と都市計画を読む。
目次
第1章 日本橋、道の始まり(橋の建設;詩歌における橋と文化 ほか)
第2章 新しい京・江戸(京に匹敵する江戸;その他の名所 ほか)
第3章 江戸聖地巡礼(江戸の宗教地図;裏鬼門 ほか)
第4章 歌枕を求めて(定まらない名所;富士山 ほか)
第5章 吉原通いの図像学(橋;建物と樹木 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
9
未開発地域だった江戸が一領地ではなく幕府が置かれることになり、京と同等いやそれを超えるべく都市開発を行う。最初は京の真似からはじまり、家光のときには世界(外国)を意識して、そして古代から続く文化の読み替え(歌枕)を行っていく。枯れ野、うら寂しい未開の地を意味した武蔵野から新しい名所や聖地を生み出していく。道の始まり、貨幣の鋳造、時の管理(鐘の音)の起点である二本橋は「日本」橋となり、それは京を超えた象徴でもあった。2015/02/10
3つ
1
都市の詩学、か。なるほど家康は、徳川家は、江戸を都にするために様々な仕掛けを施したということか。著者の陰陽道を下敷きにそれを読み解いていく手際はお見事。2024/11/10
v&b
1
第二章まで。(2019.4.11)→通しで、下読み。2019/04/11
oDaDa
1
江戸の成り立ちについての研究は多くなされているが、これは詩学という全く新しい視点から、徳川の都市計画を見直してみようとするものである。徳川が江戸を都にするにあたっては、大変な苦労があった。日本には古来からの大都市京都があり、これに並ぶ都市を醸成するには多大な費用と時間を要する。武蔵野の荒地に忽然と姿を現した江戸には歴史などなく、権威付が難しい。そこで結局は京都から多くを模倣し、こじ付け的に富士山を歌枕に仕立て上げ、更には平安時代まで遡る伊勢物語からも江戸の優位性を引き出そうとした。面白いと感じたのは、江戸2013/08/06
シュラフ
1
江戸の街は陰陽道の思想でつくられているという。江戸城を中心として、北東が鬼門。鬼門は気門(北東から南西へ気が流れる)であり、気の毒を除くために北東を守る必要がある。守るために上野の山に寛永寺を建設することで、悪い気を防ぎ、良い気だけを通す。ちなみに不忍池は琵琶湖を模したもの。山と寺院の向こう側は、刑場(小塚原刑場)や遊廓(吉原)など悪い気を放つ場を置いた。これで江戸の街の気の流れは良くなる。そして、裏鬼門となる南西には増上寺。なるほど、江戸の街の地理がこれでよく分かった。2013/02/21