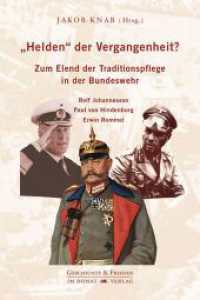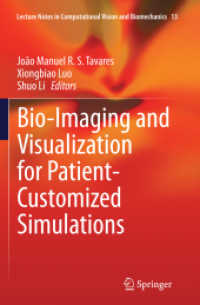内容説明
平家侵攻で焼失した東大寺を再建すること、それが東大寺番匠・夜叉太郎にとって、死んだ母と妹への鎮魂と、己の腕の見せ所だった。鎌倉期の奈良・東大寺再建秘話。
著者等紹介
岩井三四二[イワイミヨジ]
1958年、岐阜県生まれ。一橋大学卒業の頃から小説を書き始める。’96年に「一所懸命」で小説現代新人賞を受賞し、作家デビュー。2003年、『月ノ浦惣庄公事置書』(文藝春秋)で松本清張賞を受賞。その受賞第一作にあたる『十楽の夢』(文藝春秋)で、直木賞候補となる。『難儀でござる』(光文社)で大ブレイク(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きいろ
22
大仏殿焼失から再建までの、ずいぶん長い時間を夜叉太郎と共に過ごしたような気がする。 えー‼︎という最後。題名の意味がわかった。…けど、もやもや。誰も幸せじゃないよね。自業自得といえばそうなんだけど、救いがほしかったなー。2015/07/24
藤枝梅安
19
本文の最後に、明治12年、東大寺南大門修理の際、屋根裏から墨壷が発見された旨の記述があり、この作品はその墨壷にインスピレーションを得て書かれたことが伺える。平安時代末期、平家の侵攻により東大寺の大部分が焼失した。東大寺番匠・夜叉太郎はその火事で母と妹を失う。彼にとって東大寺再建が唯一の生きがいとなった。一口に「番匠」と言っても位と職務は細分化されている。一番上が「大工」、その下に「引頭(いんどう)」、「長(おとな)」、「連(つれ)」、その下に「「小童(こわらべ)」がいる。2010/09/20
真理そら
18
明治時代に南大門の屋根裏から古い墨壺が出てきた。誰が何のためにそこに置いたのか。東大寺の番匠・夜叉太郎を中心に東大寺再建の様子を描いている。東大寺が平家侵攻によって焼失したときに、母と妹を亡くし天涯孤独になった夜叉太郎は腕はいいが対人関係が苦手だ。東大寺再建のような大きい仕事ではチームで取り組む必要があり、人より木と付き合うのが好きな夜叉太郎は苦しみ苛立つ。ものづくり系の話が好きなので楽しく読めた。ただ、番匠がこれほど対立しあっていて南大門や大仏殿のような建物が無事できるものだろうかという疑問も残る。2018/03/28
Nak34
15
道念が出て来たぐらいから、期待したのですが、最後まで、不甲斐なかったですね。そんな理由なの?って、感じです。「火天の城」をお勧めします。残念。2010/09/28
のぶひこ
13
今より人生が短かった頃のお話。 能力は高いのだろうけど、だからこそなのか人物的に少しアレな夜叉太郎。もうちょっと色々とうまくやってほしいと思いつつ。 ずいぶん前だけど、東大寺に行ったとき「今みたいに重機がある時代でもなかろうに、よくもこんなに大きなものを建てたものだな」と思った。 また実物を見に行きたい。 もちろん今度は南大門を重点的に。2016/06/05