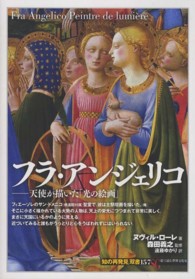内容説明
東京都下の団地の日常の中で、一人の少年が苦悩しつづけた、自由と民主主義のテーマ。受験勉強と「みんな平等」のディレンマの中で、学校の現場で失われていったものとは何か?そして、戦後社会の虚像が生んだ理想と現実、社会そのものの意味とは何か?マンモス団地の小学校を舞台に静かに深く進行した戦後日本の大転換点。たった一人の少年だけが気づいた矛盾と欺瞞の事実が、30年を経て今、明かされる。著者渾身のドキュメンタリー。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おいしゃん
55
西武沿線で、絶大な存在感を示していた滝山団地。その住民で構成された小学校における思想教育を考察する、ノンフィクション作品。同じ著者による「レッドアローとスターハウス」で、すっかり団地のとりこになったので、楽しみに読んだが、どちらかというと教育論がベースで、やや拍子抜け。そして自身の日記や文集からの引用が多々あり、長い思い出話に付き合わされた感すらある。終章に「学者が私を主人公にする物語を書くことは禁じ手とされているが〜」とあるが、まさにその心配の通りになってしまってはいないか。2015/05/26
おさむ
39
原武史さんの「黒歴史」。東久留米の公立小学校での6年間の心の葛藤を克明に綴った自伝。よくここまで鮮明に記憶しているなぁ。佐藤優さんにも似た粘着質的天才性を感じます。児童を主人公とする民主的な学校という理想を掲げて学校集団づくりが行われたが、実態は歪んだ社会主義国家のミニチュア版だった。中学受験を志した原少年は疎外感に苦しみ、塾に心の平安を求めた。1970年代前半の多摩地域における社会の断面を巧みに切り取っています。真面目な自伝だが、いま読むとお笑いに感じてしまう。時代が変わったという事なんでしょうね。2018/03/30
YO)))
17
年々マスゲーム的なものに対する嫌悪感が高まっている自分にとって、相当なディストピアみが感じられ気が滅入る話だった。 団地の均質性・閉鎖性と集団主義的教育の親和性、 そこからの逃避先が中学受験のための進学塾だったというのも、何というか皮肉だなと。2017/07/09
宮永沙織
10
1974年学生闘争が終わりを迎えたが、教育の現場では日教組による共産主義的教育がなされていた。赤旗にも掲載されるようなモデル学校に著者は小学校生活を送る事になる。2011/01/17
inokori
8
購入してから何度も中途で挫折していた一冊.著者とほぼ一回り違い,生育環境も違う自分の小学生の頃の学校の記憶と重なる部分がかなりあり,その記憶がよみがえるのが通読の妨げになってきた.コミューン形成に関わった教員たちと同窓であるという偶然も因縁めいて感じた.著者の滝山コミューンでの約10年後,あたしにも,著者が違和感を覚えた「6年5組」のようなクラスがあり,そのクラス運営を指揮する教員に目の敵にされた記憶が鮮明に思い起こされた.2010/10/24
-
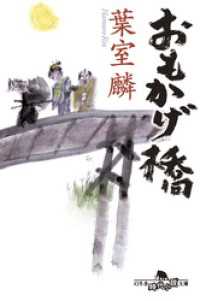
- 電子書籍
- おもかげ橋 幻冬舎時代小説文庫
-
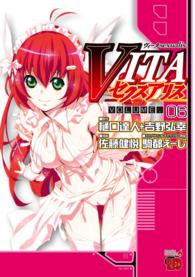
- 電子書籍
- VITAセクスアリス 〈06〉 チャン…