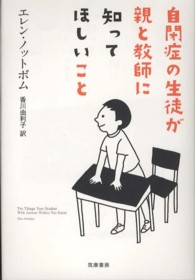内容説明
とり残された空間・学校建築にメス!子どもが「子どもをする」ところとは?人生の目的は子ども時代にある。芥川賞作家が『「家をつくる」ということ』『家族を「する」家』につづく問題作、書き下ろし。
目次
第1章 「学ぶ」ところ=学校(「母親育て」がほしい母親たち;「小学校」が子育てを奪うという不安 ほか)
第2章 「遊ぶ」ところ=ディズニーランド(眼下に浮きあがった子どもたちの「聖地」;ミッキーマウスが成人を祝った ほか)
第3章 「漂う」ところ=子ども部屋(子ども部屋は「悪」なのだろうか;もともと騒音対策室でしかなかった ほか)
第4章 「見失う」ところ=電子空間(子どもとは何だ?;テレビが子どもの思考を停止させる ほか)
著者等紹介
藤原智美[フジワラトモミ]
1955年、福岡市生まれ。明治大学政経学部卒業後、フリーランスのライターを経て、1990年に処女作『王を撃て』を発表し、文壇で一躍注目される。1992年、『運転士』で第一〇七回芥川賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Eiichi
1
今年186冊目。結局は電子ネットが今日の子どもに大きな影響を与えているという結論。おもしろかったのは、そこに至る思考過程。学校で回遊魚のように立ち歩いている子、学校でのさまざまな試行錯誤に驚いた筆者が回遊性をディズニーランド、コンビニといった子どもが夢中になる場所から子どもを観るという視点に移り、やがて電子ネットへ結びつけていくという思考。子どもを裏側から見る時、「どんなフィクションに心を置いているか」を見ていくと、ちがう見え方ができそうだ。2015/10/20
shady0004
1
「子ども部屋」の誕生にまつわる話や明治以降の学校教育で発明された「遅刻」の話など面白いものも多いが、その中にはディズニーランドがバロック建築であるというかなりの偏見がまぎれているので、内容を鵜呑みにしてはいけないと思う。(たいていの話はソースが明確ではない)2012/06/11
西
0
我田引水の気配がそこかしこで少々するものの、子供の精神の居場所について横断的に論じた興味深い本。安全の保証されたスリルとその後に訪れる安堵の癒し効果は依存症のカラクリに似ていて少し不気味。またメディアと子供の関わりについては関心があった話題なので参考になりました。2012/04/20