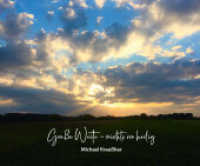内容説明
千利休茶の湯の秘伝書『南方録』から「覚書」を完全収録。日本独自の精神性と美意識がこめられた利休茶の思想は、現代人に心のありようを示してくれる。
目次
宗易ある時、集雲庵にて茶湯物語ありしに―茶の湯の心が深められるわび茶
宗易へ茶に参れば、必ず手水鉢の水を―手水鉢を使う意味
宗易の物がたりに、珠光の弟子、宗陳・宗悟と―利休の師匠
客・亭主、互の心もち、いかやうに得心して―叶うはよし、叶いたがるはあしし
露地に水うつ事、大凡に心得べからず―露地に水をうつ三露の意味
露地の出入は、客も亭主もげたをはくこと―雪駄を考案した利休
小座敷の花は、かならず一色を一枝か二枝―わび茶の花は軽く生ける
花生にいけぬ花、狂歌に、花入に入ざる花は―禁花の歌
夜会に花を嫌ふこと、古来の事なりしを―夜会にも白い花
或人、炉と風炉、夏・冬茶湯の心持、極意を―夏は涼しく、冬は暖かに〔ほか〕
著者等紹介
筒井紘一[ツツイヒロイチ]
1940年福岡県田川市に生まれ飯塚市で成長する。早稲田大学文学部東洋哲学科卒業。同大学大学院文学研究科修士課程日本文学専攻修了。現在、今日庵文庫長、京都学園大学人間文化学部教授、茶道資料館副館長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にゃーごん
4
読者は茶の湯についての事前知識があったほうがいいかなと思った。自分はまったくの素人で特に用語がちんぷんかんぷんなので、いちいちGoogleで画像検索しながら読み進めた。唯一印象に残ったのは行灯、すなわち間接照明の話。茶器類などの日本の美術品は、蛍光灯の下ではなく、薄暗い部屋で鑑賞して初めて満足できるような作品にできあがってきたはず、という著者の見解になるほど!と思った。確かに美術館でもそのように展示されていることが多いかも。芸術鑑賞は環境も含めてのことなのだと認識できた。2024/03/12
福岡英希
0
私にはちょっと難しかったです。紹オウが利休の茶会に金槌持参した話が印象に残りました。結局金槌の出番はなかったけれども。2013/07/31
magichour
0
《花をのみ待らん人に山ざとの雪間の草の春を見せばや『古今和歌集』藤原家隆》侘びます。2023/02/08
55くまごろう
0
茶道における謎の書とも言える南方録。その巻一「覚書」について原文、現代語訳、解説をまとめたもの。原文で読むのはなかなか厳しいことや、南方録全巻を通読するのもまた厳しいことから、最重要と言われる覚書をまとめてある本書は入門には最適だった。現代の茶道コースでは、形の指導が中心で、その形に至った背景や本当の「こころ」について教わることは非常に少ない。やはり自らこうした茶の湯のこころを伝える原書にあたることが、一番ではなかろうか。2020/01/21