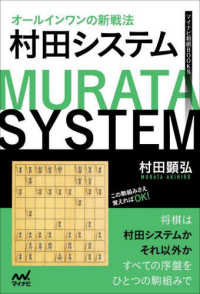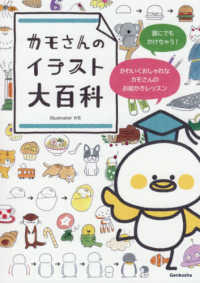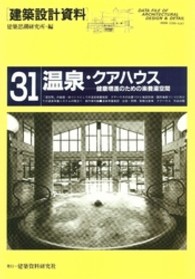内容説明
ゼノン、デカルト、カント、フッサール、ラッセル…西洋の哲学も一刀両断!インドのオモシロ深き思考の世界へ。
目次
序章 論争の王国インド
第1章 存在とことば(無はある;自己には大きさがある? ほか)
第2章 論理と知識(インドの推論は帰納的?;かたちのない知識 ほか)
第3章 世界と力(充満する力;何でもかんでも因果関係 ほか)
終章 あたりまえのインド哲学
著者等紹介
宮元啓一[ミヤモトケイイチ]
1948年生まれ。東京大学文学部卒業。インド哲学。博士(文学)。現在、国学院大学教授。専攻は、インド哲学、インド思想史
石飛道子[イシトビミチコ]
1951年生まれ。北海道大学文学部卒業。インド哲学。文学修士。現在、日本福祉リハビリテーション学院講師(哲学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
in medio tutissimus ibis.
3
インド哲学に固有なのかもっと広い範囲で用いられているのかはわからないが、使われる言葉の基本的なニュアンスが日常一般のものと違うと感じた。論理が難しいというよりも、その辺で躓いて展開される議論の内容がくみ取りづらかった。議論の対象となるのが常住の自己だとか、唯一絶対の神だとか、存在だとか、鼓腹撃壌型の人間には縁遠いものだったのもあるだろうが。オージャス(テージャス)なんぞ我にあらんや。その点では、基礎と論理の一章二章より、実生活により近いことを扱う三章から読んだ方がモチベーションを高められたかもしれない。2018/06/29
いのふみ
3
18頁最終行から急に難解になってゆくのだが。「論理」を超越しているようであったり、徹底的に論理的であったり。理解はできないが、強く惹かれる。そういう世界観だった。2016/03/24
atsushino9
1
財布の中身をあると考えよう。私の長財布の中には「お金の不在」がある。本当の意味であるのかどうかは後で考えたい。2013/10/11
チェリーブラボー
0
とっても面白かったです。この本を大学時代に読んでいれば、あんなに西洋哲学の森の中で迷子にならなくてすんだのに、とさえ思いました。同様の書をもっと読みたいと思いました2009/03/18
noharra
0
いろいろ短いトピックがあり、インド論理学の世界の雰囲気が分かる。例を引用する p65 ウッディヨータカラ:ニヤーヤ学派 主張 この生ける身体は、自己をもたないものではない 理由 呼吸などがないことになってしまうから 喩例 こきゅうなどがないものは何でも、自己をもたないことが経験されている 適用 この生ける身体もまた呼吸などがないものではない 結論 それ故に、自己をもたないものではない。(以上)2019/01/12