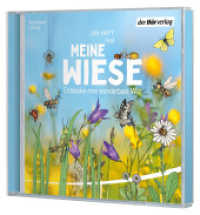内容説明
環境汚染の現場を訪ねて日本全国からブラジルへ、ベトナムへ。40年の研究成果を透徹した筆致でつづる入魂のエッセイ。
目次
水俣病は予想できた
二重の被害者
水銀の長い旅
金と水銀
マンガンという差別語
化学兵器か農薬か
毒ガス島
九州の山々で
水俣からベトナムへ
野辺山銀山の栄光と悲惨
深刻な砒素の地下水汚染
輸出された職業病
カネミ油症は終わっていない
子宮は環境である
水俣学の模索―あとがきにかえて
著者等紹介
原田正純[ハラダマサズミ]
1934年生まれ、鹿児島県出身。熊本大学大学院医学研究科を卒業、熊本大学神経精神科助手、同助教授を経て、1999年より熊本学園大学社会福祉学部福祉環境学科教授。1964年に胎児性水俣病の研究により日本精神神経学会賞、1989年『水俣が映す世界』(日本評論社)で第16回大仏次郎賞、1989年『水俣―もう一つのカルテ』(新曜社)で第31回熊日文学賞、1994年に国連環境計画(UNEP)からグローバル500賞、1997年南日本文化賞、2001年には熊日賞、第35回吉川英治文化賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
2
情報が正しく伝わっていない場所では、被害者は単に直接的な問題だけでなく、周囲からの目という別の問題にも対処しなければならなくなる。特に、相手が強大なものになってくればくるほど、そのような誤解をとくために必要なコストは大きくなる。時間が立てば真実が解明されるとしても、それまでに受ける被害は決して無視できるようなものではない。2015/04/16
あきら
0
水俣病。もうなくなった過去の公害だと誰もが思っているだろう。けれど、生涯ずっと水俣病の研究に費やしてきた原田正純教授の、水俣病とその他の公害病の記録ともいうべき一冊。細かい年度が書かれているけれど、驚くべきことに、わりとつい最近の西暦が出てくる。pm2.5をあたかも悪魔の公害のように騒ぎ立てているけれど、そういえば日本はつい最近まで公害立国だったなと思い知る。というか、今でもそうだわ。救済を求める人は平成も終わろうとする今もまだなくならない。けれど、原田正純教授のような人はいない。2018/10/28
-

- 和書
- ことばの心理学 中公新書