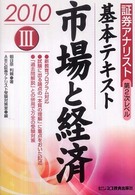内容説明
大学ノート七冊分の日記を見つけたのは去年の6月の終り、帰省先の生家の二階の隅でだった。日記は、日本語の内容がロシア文字で表音化されていた。ロシア字日記の“翻訳”から炙りだされる「おどるでく」の正体とは?忘却されたものたちの声なき声を描く表題作ほか、一篇を収録。ほとばしる才気、卓越したユーモア、幾重にも重なるエピソードの迷宮。群像新人賞作家の不可思議な世界。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
156
第111回(平成6年度上半期) 芥川賞受賞。 実家の二階で見つけた祖父の ロシア語の大学ノート。 それを読みときながら、 物語は進む。だが、露文氏が 描く大学ノートの世界に 私は入り込めなかった。 ロシア語などの言語研究に 明るい人は面白いかも しれないが、残念ながら 私にはよくわからなかった。2014/09/11
kaizen@名古屋de朝活読書会
92
何がなにやらさっぱり分からない。「おどるでく」が何か。なぜロシア文字でかながきしているのか。ロシア文字による仮名書きって何。時々出てくるロシア語を調べる気にもならない。「くでるどお」でも気にならない。いろいろ文学作品名が出てくる。半分は読んだことがない。興味がなかなか沸かない。不思議な話。2013/12/04
ヴェネツィア
62
1994年上半期芥川賞受賞作。室井光広は初読。表題作の存在も知らなかった。読む前は、ひらがな表記のタイトルは漢字をあてれば「踊る木偶」であろうと、朴訥な主人公の農民文学のようなものを想像していた。結果的には全く違っていて、実に難解な小説だった。「おどるでく」の実態は、カフカのオドラデクのようでもあり、またそうでもなく、結局は判然としないままに終わるのである。そもそもロシア文字を用いて書かれた日本語の日記も、小説中に鏤められたオラショ等の数々のモチーフも統体としてのメタファーとしてしか了解できないのだ。 2013/08/21
おにぎりの具が鮑でゴメンナサイ
18
ブンダンの評価とか高尚ブンガクとかの理解ができないのはおれが精神病だからにちがいない。貴族の糞だからって美味しくはない。赤ん坊の泣き声の方がまだ意味くらいは何となくわかる。信者のいない教祖が唱える独り言ははたして神の教えで誰かを救うのか?需要もないのに砂漠のど真ん中に伊勢丹を建てるのか?南極でおでん売ったら儲かるのか?チョコボールに金のエンゼルって本当にあるのか?この世の中にはわからないことが多すぎてロシアの病院に強制隔離されたくなった。そこで読もう、何年かかけて。2014/04/18
大粒まろん
14
あーこれも、芥川賞全部読むでなければ、ロケットに括り付けて、宇宙に飛ばしたい作品でした。これはもう、出版社が草稿を編集できる者がいないから、そのまま原稿として印刷にかけたでしょ笑。兎に角、読み手が不在の書き物。読者はほったらかしです。謎の仮名書露文さんの日記の論評を読みたい訳でないのですが笑。それとロシア語はキリル文字と書いて欲しい。この表記がないのが気持ち悪くて仕方ない。あと、図書館の仕事は無味感想とかでもないし笑。しかし、これが頭の中で宇宙的に展開してるのであれば、凄いことではある。2023/06/05