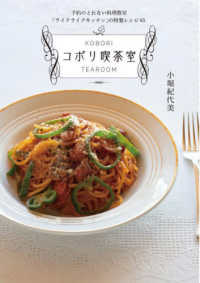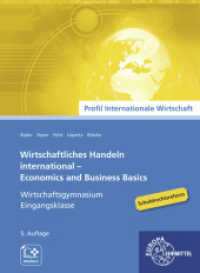内容説明
夢、幻想、欲望の中に浮遊する「私」というカオス―さまざまな仕掛けで存在の謎と闇に迫る十一篇。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パラ野
11
高橋たか子「骨の城」なんとも切なくなってくる。吉田健一「一人旅」ねじれが象徴的。散文詩のような。中里恒子「家の中」フェティッシュな生活だな。宝箱で暮らしているようだ。三田誠広「鹿の王」もののけ姫。「私」の変容と過去の逆襲のよう。忘却ではないので、悲劇にはならない。鹿の王からの語りと人間たちの知覚の違いに注意。小林恭二「磔」ネット上での私」のコントロールについて考える。森瑶子「死者の声」見る私/書く私/見られる私/欲望される私、幾つかの分裂を抱える。2014/09/21
kakekoe
7
装丁に魅かれ昔々に買った本。戦後50年間に発表された11の短編は、当然書かれた時代背景にばらつきがあり、どれも粒選りなんですが、一つ読み終えてから次を読み始めても、作品世界にすうっと入れないもどかしさがありました。個人的には遠藤周作の『イヤな奴』が今の自分に一番響きました。中里恒子の『家の中』も自分のこれからと重なりそうです。2024/01/28
里馬
4
安部公房、遠藤周作、小林恭二を除き八名初読。殆どどれも好みだったけど島尾敏雄「夢屑」にどきどき。2011/02/21
かふ
3
梅崎春生の他人の中に潜入する「私」、遠藤周作のイヤな奴な「私」、高橋たか子のMかもしれない「私」、吉田健一の一人旅の男を文章で追っていく「私」、島尾敏雄の夢屑な「私」、安部公房のカフカ的「私」、中里恒子のひとり家の「私」、小川国夫のパウロの棘が抜けない「私」、三田誠広の鹿と王を巡る「私」、小林恭二のネットをする「私」、森瑤子の作家だから男なんて登場人物よという「私」。一部題名そのままのものがある。ベストは安部公房の『ユープケッチャ』かな。他に梅崎はちょっと気になる。中里恒子は、見習いたい。2011/01/16
三柴ゆよし
2
梅崎春生「鏡」において、「松尾老人」は「私」の抑圧された影の部分を映し出すいわば反面鏡としての他者だが、遠藤周作「イヤな奴」では、「私」の肉体と精神は引き裂かれ、それぞれ「飯島」、「大園」という両極的人物の姿をとって現われてくる。高橋たか子「骨の城」はコメントに困る作品で、島尾敏雄「夢屑」のほうがまだしもわかりやすい。とまれ、どちらも幻想のありかたが好みだったのでおもしろく読んだ。小林恭二「磔」はやや異色。情報の背後に存在する不特定多数の「私」を描いているように思われる。わるくはないアンソロジー。2010/05/26
-

- 和書
- アメリカ名詩選 岩波文庫