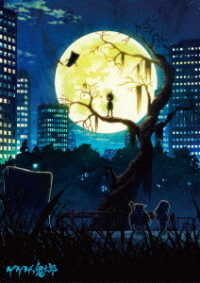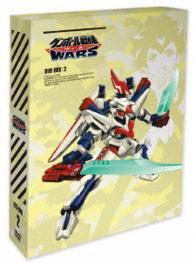内容説明
「蔵の中」「思い川」「枯木のある風景」などの名品を残した著者は、また文芸評論にも筆をふるい評論家としてのひらめきを発揮した。本書は、斎藤茂吉、永井荷風、森鴎外、里見〓、川崎長太郎、稲垣足穂、島木健作等をはじめ、親しかった加能作次郎、牧野信一、葛西善蔵、嘉村礒多の思い出を、機知に富んだ独得の文章で綴った作家論。文学の鬼と称された宇野浩二の真骨頂。
目次
斎藤茂吉の面目
折口信夫という人
愛読する人間
文芸放談
哀傷と孤独の文学
里見〓
川崎長太郎
稲垣足穂と江戸川乱歩
独断的読後感
忘れ得ぬ一つの話
『大菩薩峠』について
文芸よもやま談義
著者等紹介
宇野浩二[ウノコウジ]
1891年(明治24年)7月26日生まれ。1910年(明治43年)4月、早稲田大学英文学科予科に入学。1913年(大正2年)4月、白羊社書店から小品集『清二郎夢見る子』を処女出版。1915年(大正4年)3月、早稲田大学中退。1940年(昭和15年)3月、第二回菊池寛賞を受賞。1949年(昭和24年)1月、芸術院会員。1951年(昭和26年)5月、「思ひ川」により第二回読売文学賞を受賞。1961年(昭和36年)9月21日、死去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shinano
19
宇野浩二という大正期に活躍した作家が読書メーターで感想コメントを書いているような感じでよかったと思っている。尊敬する作家文人や親交ある作家の、作品とその人間について、自論と他論を織り交ぜて、まわりの作家仲間から『文学の鬼』と呼ばれ純文学への思い入れたっぷりに独特の文章で書かれている。名は聞いたことがあるがその作品については未知だった作家たちについて、宇野の感情や論旨で瞠目させられ是非とも読んでみたいとの欲求にかられてしまった。宇野が自分の意見の補強に引用する友人作家広津和郎は宇野の重要人物と確信した。2011/08/27
ポカホンタス
3
研究の必要上、冒頭の「茂吉の面目」だけ読んだ。茂吉の散文には名文が多いことを紹介。茂吉の面目がそのまま出ているから名文だという。「接吻」「手帳の記」「翌日」「ユングフラウ行」などを取り上げている。茂吉の人となりについての分析も面白い。 「茂吉が向きになればなるほど、おのずからの愛嬌と諧謔の出ている文章」 「ドキドキ不思議なエロティックなようなものも現れ、普通の人間には書けないうような事さえも書かれている」 人柄ではなく、面目と表現する宇野の面白さ。2020/04/12
AR読書記録
2
読んでいると、この人編集者なんかな...と思う感じの、「文学」との関わり方。作品を作品だけでなく作家からも読み、また自分の思い入れも混ぜる感じの。いやそれが良いとか悪いとかでなく、いかにもある時期の「文学」て感じやのう、と思っていたが、解説の「文学は、やはり文学が青春の同義語として神話化され、文学青年が憧れの対象とされた時代の歴史的産物だったのだ」という一文に膝をうつ。いや、自分に都合のよい読み方っぽいけども。2017/05/03
ほたぴょん
1
小説を読むのが好きな作家というのはもちろん多いのだが、その中でも横綱級だと思うのが川端康成と宇野浩二である。宇野は芥川賞の選考委員を長く務めたが(しかも一度退いてから、また請われて再就任している)、これはその証左であると同時に、宇野の小説を読む目が買われていたことを証するものでもあろう。文体に独特のクセがあり、とにかく思いついたことは全部書こうとしているようにも見えるが、これも芥川賞の選評の頃と同じで、宇野の選評はだいたい長文になるのが常だった。卓抜な評論ではないかもしれないが、好ましい一冊であると思う。2013/12/01