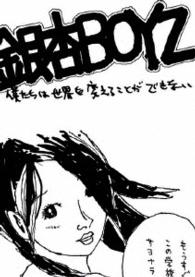内容説明
短歌、俳句、演劇…さまざまなジャンルで煌めく才能を発揮し、四十七歳で逝った寺山修司の詩的感性が横溢するエッセイ集。偏愛したボルヘス、夢野久作、フェリーニ等についての洞察、自叙伝、芝居、競馬等のエッセイを収録。
目次
1 私という謎(黙示録のスペイン―ロルカ;父親の不在―ボルヘス;鏡―ダリ ほか)
2 旅役者の記録(旅役者の記録;女形の毛深さ;サーカス ほか)
3 自伝抄(汽笛;羊水;嘔吐 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハチアカデミー
14
寺山はいまだって新しい。私に拘りつづけた日本文学にあって、如何に己から飛躍できるかを目指した彼の作品群は異彩を放つ。彼が好んだ作家を取り上げたエッセイ、旅にまつわるもの、そして嘘と作為まみれの自伝からなる本書は、寺山修司の本質(なのか実存なのか)がよくわかる。捨てられた鰐に注目するピンチョン「V」評が印象に残るが、それ以上に本当のことと嘘が入り交じる、己の「母」への思いを描く三章がおもしろい。嘘を語っても、そこに描かれるイメージや願望は実際に寺山が抱いたものであり、そうなると本当と嘘の境が溶けていく。2013/10/14
あなた
13
わたしたちは、なにかを「いわない」ために、そのことを「いいつづける」のだということをよく知っている。おそらく「私」とは、そのはざかいにある「引き裂かれ」のことだろう。「書も捨てず、街へも出られず」『家出のすすめ』を書きながら、結局「イエ」を出ることさえ、かなわなかった。否定というのは最高の肯定の形態なのである。「『家出のすすめ』を書いてるんだよ」「ああ、あたしも賛成だよ。家出するなら、母さんも一緒に行ってあげるからね」2009/09/11
六波羅
11
寺山修司と言えば、演劇、映画製作、エッセイ、俳句、短歌、詩などマルチな活動で現在も後進に影響を与え続けている人物だ。その活動のなかで、僕の注目する寺山修司のキーワードは「競馬」「母親」の2つ。「競馬」は昨今の風潮からすれば浪花節全開なので好き嫌いあると思うが、逃げ馬(脚質が逃げの競走馬)と逃亡を続ける人物を重ね合わせる手法は見事だと思う。次に「母親」寺山修司が過去を改竄して作り上げた、虚構の母親。母恋しや母憎しの俳句や短歌。僕はそれらを読むと正直嫌な気分になる。絶縁して久しい母親を思い出すからだ。2014/10/19
あくび虫
3
確かにエッセイなのですが、なんとなくエッセイではない。一冊の哲学書のようであり、小宇宙で、虚構。通底する思想を感じながら読んでいると、「これはいったい何が事実なんだろう…?」と迷宮に入り込んでいく気分になります。それくらい絵的でドラマティックさがあります。2018/07/27
ダージリン
1
初めて寺山修司を読んだが、熱いファンがつく理由が良く分かった。自分を突き放したかのような距離の置き方、視点の置き方は確かに格好良い。実に良く見られ方を意識している文章と思えた。ただもう少し演出を抑えた素直な書きっぷりの方が個人的には好みではあるのだが。2018/05/10




![ワンワンといっしょ! 夢のキャラクター大集合 ~センターを取るのは、だれだ!?~[Blu-ray] Blu-ray Disc](../images/goods/ar/web/vimgdata/4549767/4549767024189.jpg)