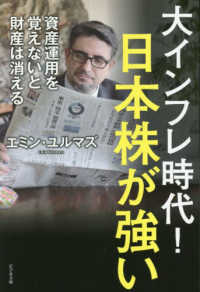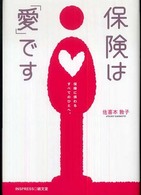内容説明
戦争後遺症のラグーナ・プエブロ族の混血の青年テイヨの身心は軍の病院でも治療できない。頼みは部族伝統の儀式。メディシン・マンのベトニー老人は治癒への“新しい儀式”と砂絵を示す。自然の知恵、愛、自己の認識。口承文学の香り高き寓話と詩を自在にとり入れつつ、第二次世界大戦後の“アメリカ・インディアン”の若者達の厳しい現実を描出。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
拓也 ◆mOrYeBoQbw
20
ネイティヴ・アメリカン文学。二次大戦の南太平洋のジャングルから帰還し、心を病んだテイヨ。ネイティヴの血を半分継ぐ彼を取り巻く過去と現在、そして治療の為に一族のメディシン・マンの”新しい儀式”により語られた”物語”を辿る。時間軸と主観が入れ替わり、更に伝承の歌が度々挿入される形式ですが、表現は分かり易く『失ったものを取り戻し、帰ってくる』基本中の基本で読み易いと思います。作品通じて混血テイヨを通じて語られる、大戦を挟んだ北米のダークサイドが最も強い印象として読後に残る感じです。力のある一冊でした(・ω・)ノ2018/07/14
長谷川透
17
白人の介入で、アメリカ・インディアンは血縁的地縁的な居場所を解体され白人社会の中に強引に取り込まれた。強大な国家の虚構性が、語り手の口承の物語の中で次第に露わになる。国家とは巨大な虚構に過ぎないのかもしれない。国土も国民も法も、国家という虚構が創られた後に二次的に誕生する。生れ落ちた時から虚構の中に居ては虚構を虚構と思わないだろうが、突然、その中に取り込まれた者は自らの血縁的地縁的現実と虚構との間でどのように振舞えばよいのか。儀式はテイヨだけではなく、誰もが現実へ回帰する足掛かりになるかもしれない。傑作。2013/02/19
ハチアカデミー
13
A+ 物語が人を救う。混沌とした歴史や事件、個人の感情に輪郭を与え、ストーリーを作り上げる。それは夢でも幻想でも良い。土地には、膨大な過去が眠っているし、人間の脳は現実を越えることさえできる。太平洋戦争に連れ出されたインディアンとメキシコ人のハーフであるテイヨが、戦争の精神的後遺症から抜け出すために、インディアンの伝統的な「儀式」を受けることで、病から回復する物語。時系列が入り乱れ、死者が現実に介入する。断片的な語りに詩や寓話が挿入され、ひとつの大きな流れとなっていく。手法もメッセージも力のある作品。2013/02/06
AR読書記録
6
『アメリカの黒人演説集』の訳者の方だから...と読んでみました。海外文学は訳者が誰かが、選択の大きな導きになるものです。というのはともかく、ストーリーとしてはわりと難解。一度でちゃんと追えたとは思えない。が、十分に考えること、思考を迫るものは多く受け取ったつもり。科学というのは、確かに今現在、世界を捉えるツールとして信頼性も(まだ?)高く重要なものだとは思うけれど、だといって、他のツール(例えばインディアンにおける“物語”とか)を頭ごなしに否定してよいものではないだろう、とか。原爆まで出てきて、瞑目。2016/12/06
の
4
第二次世界大戦のPTSDに苦しむインディアンの青年が、部族の儀式で立ち直ろうとするもの。章の間に挿入される民俗口頭詩が嫌が応にも哀愁を漂わせ、抑圧され文化を殆ど失ってしまった現代インディアンのアメリカ社会での様子との対比が、アイデンティティ・クライシスとアイデンティティの強さを自動的に物語る。PTSDの直接の原因が「倒した日本人に先祖の顔を見た」のも不思議だが、言われてみれば同じモンゴロイドであると考えられており、その為、相手の苦しみを理解してしまったのではないだろうか。多くの人に読んで欲しい米文学。2011/05/14
-
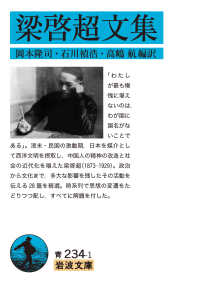
- 和書
- 梁啓超文集 岩波文庫