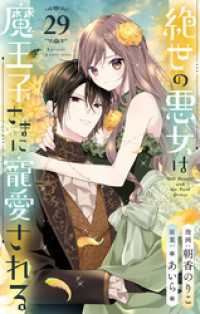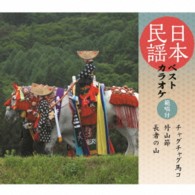内容説明
生命の鍵をにぎるDNAモデルはどのように発見されたのか? 遺伝の基本的物質であるDNAの構造の解明は今世紀の科学界における最大のできごとであった。この業績によってのちにノーベル賞を受賞したワトソン博士が、DNAの構造解明に成功するまでの過程をリアルに語った感動のドキュメント。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
135
DNAの二重らせんを発見するまでのドキュメントというかその過程をご本人の口から説明してくれます。ただやはりこのような本を読んでいると普通の人間にはやはりできないだろうな、という感慨が浮かびます。どこか性格的な問題があったりとかあるいは目の付け方が普通の人とは違う気がします。ただドキュメントとしては面白いと感じました。2016/03/24
maimai
36
現代の医療や捜査に大きな影響を与えているDNA。それがワトソンとクリックにより発見されるにいたった経緯が描かれているドキュメンタリー小説です。自分は生物に関する知識が無いのでよくやく分からなかったのですが、DNAの二重螺旋構造の発見は偉大なものであったということ、研究者たちの研究ができる喜び、熱意は伝わってきました。大発見に繋がることをする人って人並外れた情熱を持っているのですね。そしてその発見は後世まで語り継がれて、自分たちの生活の助けになってくれたりもする。昔の人たちに対して尊敬の念が湧いてきます。2016/06/29
Willie the Wildcat
33
熱意、閃き、そして運。可能性を拡げる人脈。積み重ねた事実と推察を、X線、結合、そして模型で”姿”を見せ始める過程が秀悦!特に印象深いのが、ジェリーのSME見解。A-T/G-C。偶然が必然性となり、必然性が偶然となった瞬間。1つのことに吸い込まれていく研修者仲間。研究過程における過渡の競争意識・見下すかのような言動も、強い思いの表れ!ポーリング・ピーター親子の”距離感”も研究者故だが興味深い。求められる変化とスピードに、現代ビジネス界を彷彿。正に人間ドラマ!2014/09/25
kazuさん
32
ケンブリッジにあるキャヴェンディッシュ研究所を舞台に繰り広げられたDNA二重らせん発見の物語。ワトソンとクリックの格闘が生き生きと描かれている。競争相手は、ロンドンのキングスカレッジにいたモーリスやフランクリン。更には、カリフォルニア工科大学のポーリング。主に3つの研究グループが息を呑むような発見のレースを展開する。2人は女性研究者フランクリンのDNA解析データを参照して、実験せずにDNAモデルを完成させた。本文の大半で彼女を腐してばかりだが、最後には早逝した彼女を讃える論調に変化している。2022/02/14
紫羊
26
もう遠い昔のことだが、理科の先生が絶賛していたことを思い出す。「とにかく面白い!騙されたと思って読んでみなさい。」と、興奮気味に生徒に勧めていた。私は理系の学問には全く興味がなかったので、何の迷いもなく先生の熱心な勧めを無視した。今回初めて読んでみて、今の私よりもずっと若かった先生が、この本に胸を躍らせた気持ちがわかるような気がする。世紀の大発見の記録というより、どこにもいるような若者の青春小説を読んでいるような気分だった。確かに面白かったですと先生に伝えたい。2013/11/19